沖繩県八重山地域における家畜防疫衛生業務および肉用牛生産振興の取組み
――家保を中心としたオウシマダニ撲滅と牧養力の向上――
那根 元
◎畜産大賞最優秀賞:指導支援部門沖繩県八重山家畜保健衛生所 |
1.指導支援業務の概要
昭和47年5月の祖国復帰に伴い中央家畜保健衛生所八重山支所が設置され、平成4年4月に八重山家畜保健衛生所(以下・家保と略す)に昇格する。組織は防疫衛生課と振興課および与那国駐在の2課1駐在体制である。〈家畜防疫衛生業務:防疫衛生課〉
- 地域の家畜衛生業務の企画調整
- 家畜の伝染性疫病の予察・予防、駆除・清浄化・撲滅、蔓延防止
- オウシマダニ駆除・清浄化・撲滅対策
- オウシマダニが媒介する法定伝染病バベシア病
- 風土病・沖繩糸状虫病の清浄化対策
- 畜舎・牧野衛生
- 家畜の繁殖障害の改善
- 畜産経営の改善および指導普及事業
- 優良家畜の増殖普及、人工授精の精液払受けおよび指導督励
- 牧野および草地改良の指導、施設・草地開発の実施計画策定指導
- 団体営草地開発事業
- 里山等利用促進事業
- 畜産基地建設事業(スタビライザー工法)
- 畜産経営環境保全
- 畜産および畜産物の流通・価格の調査指導

実績を発表する筆者
家保は県畜産会、家畜改良協会、市町、農協、石垣島和牛改良組合等と連携を密にし経営診断の指導を行い、優良系統牛の改良、流通、牧野ダニ撲滅に取組んできた。
- 1) 牧野ダニの被害
- 牧野ダニ(オウシマダニ)が媒介する、法定伝染病であるバベシア病やダニの吸血等により大きな被害損耗を被っていた。
- 昭和46年度から、本格的な牧野ダニ対策事業がスタートしダニ駆除、清浄化、撲滅事業を継続実施してきた。
-
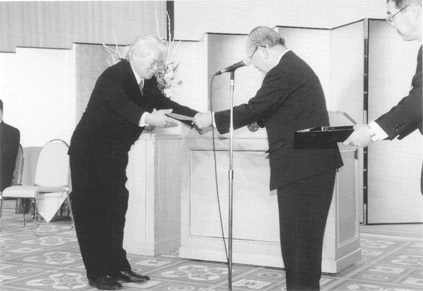
- (社)中央畜産会桧垣徳太郎副会長より平成11年度畜産大賞・指導支援部門で最優秀賞を授与される
- 牧野ダニ清浄維持事業によって、平成5年2月以降のバベシア病の発生がなく、また、平成5年度以降はバベシア病原虫の確認がされず、さらには平成6年度以降は草地ダニおよび牛体ダニも確認されていない。
- それによって、平成11年4月から牛の移動制限が解除された。
- 2) 牧養力の向上
- 昭和51年度からはじまった、公団営による畜産基地建設事業の導入によって末利用、低利用地が草地造成された。
- 平成9年度までの造成面積(スタビ工法も含む)は1337ha、参加農家133戸、事業費は229億9518万円が投じられた。
- これによって牧草地の粗飼料生産量が著しく増大し、畜産施設の活用と管理技術の普及によって飼養頭数が増加し、牧野ダニの撲滅と相まって着実に牧養力の増大が図られてきた。
2.指導支援の内容
八重山家保は、1市2町からなる八重山地域全体を管轄している。八重山地域は北緯24度3分〜25度25分、東経122度56分〜124度20分の範囲に位置し、有人島11島、無人島20島からなっている。
有人島は石垣市1島、竹富町9島、与那国町1島であり、航空交通については、波照間島、与那国島が石垣島との間を1日1往復、また海上交通については、新城島を除く各有人島と石垣港との間に定期便が運行されている。
肉用牛は、すべての有人島で飼育されているが、八重山地域における肉用牛の飼養状況は、昭和47年当時で飼養戸数1317戸、飼養頭数7561頭であったのが平成3年には852戸、2万0170頭、平成10年12月末では961戸、3万6140頭と増頭し、県総飼養頭数約7万8000頭の46%を占めるほどに規模が拡大された。

受賞祝賀会で夫婦揃って挨拶する筆者
昭和47年度の八重山地域の農業粗生産額は20億7000万円であったのが、平成3年には110億4500万円に伸び、平成9年度は122億2500万円で畜産部門の63億4000万円、うち肉用牛部門が56億4200万円と農業粗生産額全体の43%を占め、地域の基幹作目のトップに位置している(表1)。
|
|
|||
| 戸 数 | 頭 数 | 1戸当り頭数 | |
| 石垣市 | 637 | 27,378 | 43 |
| 竹富町 | 222 | 6,528 | 29 |
| 与那国町 | 102 | 2,234 | 2 |
| 八重山計 | 961 | 36,140 | 38 |
| 県 計 | 3,523 | 78,660 | 22 |
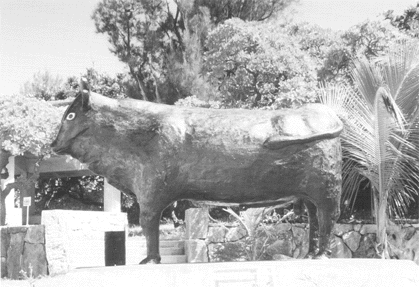
黒島は「牛の島」ということで港には牛の像がある
平成10年には115億7800万円で畜産部門は66億300万円、うち肉用牛部門が59億1100万円で57%を占め堅実な伸展を続けている。
- 1) 指導支援の開始
- 2) 指導支援の位置づけ
- 3) 指導支援の実施体制
- 4) 具体的な支援指導の内容と成果
- 5) 支援指導の活動の年次別推移
八重山地域の肉用牛は、自然草地を主体にした周年放牧で省力的、粗放的な管理がなされていた。しかし、肉用牛生産拡大のためには、旧態依然たる粗牧的な経営では限界があり、草地基盤の整備拡大、農業用施設さらには農機具の整備等が要望されていた。
そのような背景から、自給飼料生産によるコスト低減と農家所得の拡大を図るため、飼料生産基盤の整備を推進している。
そのおもなものは、公団営畜産基地事業(昭和51〜平成4年度)、団体営草地開発整備事業(昭和47年度〜)、農業公社牧場設置事業(昭和50〜平成5年度)、公社育成牧場整備事業(昭和47〜56年度)等である(図1・表2)。
また、平成5年度より畜産基盤再編総合整備事業を実施しているところであり、今後は未墾地、遊休地等の造成改良、生産性の低い草地等の整備改良等を推進し、飼料生産基盤の拡大整備を図る計画である。

長嶺畜産の放牧地
肉用牛の改良に関しては、先進県からの計画的な優良種畜の導入、人工授精普及推進事業、計画交配事業および肉用牛群改良基地育成事業等を推進している。
流通に関しては、家畜市場および食肉センターの整備を実施した。
経営面においては、地域環境との調和にじゅうぶん配慮し、耕種との結合を深め、急激な畜産情勢に対応できる競争力の高い経営体を育成するため、畜産経営技術高度化促進事業による指導を強化している。
牧野ダニ対策としては、昭和46〜52年度まで「石垣島牧野ダニ駆除事業」および「沖繩牧野ダニ駆除促進事業」により、薬剤の空中散布および地上散布による草地ダニ駆除並びに牛体薬浴による牛体ダニ駆除の両面作戦によって、一定の効果をあげた。
昭和53年度から、沖繩牧野ダニ清浄化対策事業を継続し全体的に殺ダニ効果をあげ、特に昭和61年度から、離島の黒島をダニ撲滅重点指導牧野と位置づけて、ダニ撲滅の原則である「1頭のもれなく」を合い言葉にダニ駆除を実施し、平成2年に黒島において八重山地域でははじめてオウシマダニ撲滅を達成した(図2)。
平成3年度からの「沖繩牧野ダニ撲滅対策事業」まで継続して、竹富島、小浜島、鳩間島、波照間島、西表島並びに与那国島の1つひとつの島を、段階的にダニ撲滅重点指導地区に設定して事業を推進した。
八重山地域の牛総飼養頭数の70%を占める1万6000頭を飼養し、周年放牧や繋牧等の飼養形態および地形的にもダニ駆除が困難であると考えられた石垣島のダニ撲滅対策事業を、平成4年10月から「1島1牧場」の理論で、全島いっせいに実施し平成7年に清浄化、平成8年度から開始された「沖繩牧野ダニ清浄維持対策事業」において、平成8年にオウシマダニの撲滅が確認された(表3)。
現在は、平成11年度終了予定で最終段階の牧野ダニ清浄維持対策事業を実施している。
古くからのダニとの闘いのなかで、春から秋までの期間は、ダニの発生に伴うバベシア病のまん延によりへい死牛が増加、生産子牛もダニ吸血に起因した栄養失調等により、育成率が50〜60%であった。また、大部分の離乳子牛も削痩を呈し発育不良で、死亡率も高く、子牛の価格も低かった。
牧野ダニ駆除事業の推進により、平成元年ごろから急激にダニの個体数が減少したため、バベシア病やダニ吸血による被害も減少し、生産率、育成率の上昇に伴い、畜産農家のダニ撲滅へのいっそうの意欲と期待が盛りあがり、撲滅へとつながった。
このダニの撲滅、ダニが媒介する伝染病等の克服によって、これらに係る畜産農家の労働が大きく節約されたこと、また、牧野・草地改良によって、牧養力が1ha当り1〜3頭近くまで増大したことによって、肉用牛経営の規模拡大が可能になり、着実に進展した。
また、ダニ撲滅、伝染病等の克服、より良質な牧草飼料の生産によって、健全な繁殖牛の確保、健全・良質の子牛生産が可能になり、子牛の価格が上昇してきたことによって経営規模の拡大が進み、農家の所得も向上した。
以上、既存の肉用牛経営の規模拡大、それに加えて、他作物からの肉用牛への転換、離島の他産業従事者の帰島による肉用牛経営者の増加、高齢農業者の意欲向上と作業条件の改善による肉用牛経営の長期継続を可能にし、当地域の肉用牛生産振興、地域の活性化に重要な貢献を果たしている。
生産率、育成率の向上について
| (1) | 全郡的に畜産施設の完備、未利用、低利用の草地基盤の造成事業(スタビ工法)により導入草種の選定、草地管理技術、牧養力の拡大が図られた。 | |
| (2) | 母牛の増飼い、子牛別飼い、放牧管理、飼養管理技術の向上により、経営感覚が高まり、記録、記帳をもとに、経営診断を継続してきた。 | |
| (3) | 系統的に糸桜系を中心に質量兼備の母牛集団を造成し、県の改良方針に基づいた交配計画を実施してきた。 |
八重山地域の畜産振興推進に関しては、図3に示すように地域指導体制のとおり、家保振興課を中心として、県畜産課、農業改良普及センター、畜産会、市町および農協等の関係機関と連携した飼料基盤整備事業、肉用牛改良推進、流通および経営指導等の対策・指導を実施している。
また、家畜防疫衛生業務は、家保防疫衛生課を中心として家畜伝染病予防事業、家畜衛生技術指導事業、牧野ダニ対策事業および家畜衛生に関する普及啓蒙を実施している。
沖繩牧野ダニ対策事業は国、県、市町等生産農家の一体となった長年の粘り強い努力によって実現した成功事例であり、オウシマダニ撲滅は世界的にも例をみない成果である。
八重山地域における当該事業の推進においては、県家畜衛生試験場の技術支援のもとに八重山家畜保健衛生所を核として、石垣市、竹富町、与那国町を主体に農業協同組合、和牛改良組合、肉用牛生産組合、牧野組合、家畜診療所、農業共済組合、農業改良普及所および他家畜保健衛生所等、畜産関係機関を網羅した組織体制により着々と実施された(表4・図4)。
その協力体制に基づいて国、県としては牧野ダニ駆除指導および草地ダニ、牛体付着ダニ調査、牛採血によるバベシア原虫、住血微生物等の精密検査を年間をとおして確実に実施してきた。
飼料基盤の整備に関しては、図5のとおり国、県畜産課、農業開発公社および市町と連携のうえ、諸事業を推進している。
また、家保に暖地型牧草種苗圃を設置して、畜産農家に対して直接牧草の種苗・種子を払下げ、自給飼料の生産拡大を支援している。
草種としてはジャイアントスターグラス、パンゴラグラス(A―24、トランスバーラ)の種苗とナツユタカの種子を有償で払下げている。
| (1) | オウシマダニの撲滅および沖繩糸状虫症対策 |
昭和47年ごろの八重山地域における肉用牛の飼養形態は放牧60%、舎飼い20%、繋牧20%の割合であり、事業推進において、特に繋牧方式は自由に牛を移動するために1頭1頭の確認が困難であり、また、ダニ駆除のための牛群の集合についても厳しいものがあった。そのため、繋牧を舎飼い方式に改善させ、大きい面積の放牧場、あるいは輪換放牧においては、山岳地域には牛が入らないように牧柵等を設置させた。
併せて、牛体薬浴施設についても地方競馬全国協会、草地開発事業団等の補助事業、および畜産組合、個人の資金によって着実に整備・増加させた。
しかし、昭和60年度までに沖繩本島および周辺離島、並びに宮古群島のほとんどの地域で、オウシマダニが確認されなくなったにも係わらず、八重山地域では依然としてオウシマダニが棲息し続ける状況にあった。そのおもな原因として、対象範囲が広すぎることに起因する可能性があることを踏まえ、昭和61年度から、一部地域ごとにダニを清浄化する方法を取入れ、黒島を重点指導地区としてダニ駆除指導を開始したが、従来のアズントールの使用濃度ではじゅうぶんなダニ駆除効果が得られず、牛が中毒症状を呈して死亡する例もあった。
県家畜衛生試験場の調査により、有機燐系あるいはカーバメイト系殺ダニ剤に対する抵抗性ダニが存在し、ピレスロイド系の殺ダニ剤しか有効なものがないことが判明した。黒島では、平成元年から使用されはじめたフルメトリン製剤を含め、ピレスロイド系殺ダニ剤の使用により、オウシマダニが全く確認されなくなった。
また、同時期に開始されたフルメトリン製剤を用いたプアオン法は、従来の薬浴法に比べ、はるかに効率および省力的で優れており、今後のダニ駆除法に、新たな転換期を迎えさせるものであった。
プアオン法を取入れた「沖繩牧野ダニ撲滅対策事業」の推進に当っては、畜産農家の啓蒙を重視し、「1頭のもれもなく」を合い言葉に、牛の個体番号の装着と台帳作成を徹底、ダニ駆除作業の際に厳重にチェックを行った。その際、1頭でももれがあった場合には、台帳と合致するまで徹底して駆除作業を実施した。
風土病として知られている沖繩糸状虫症については、国庫補助を得て、昭和53年度から薬剤投与による対策を実施してきたが、近年、本病の新たな発生はみられない状況にある。
以上のような生産阻害要因の除去により、肉用牛の生産率および育成率の向上が図られ、ダニ駆除作業からの解放と労働時間の節約、牛の移動制限解除に伴う手間・経費の節約、さらには商品としての子牛のイメージアップが図られ、生産者の意欲が大いに向上した。
| (2) | 牧野・草地の基盤整備、改良 |
畜産基地建設事業、団体営草地開発整備事業等の飼料生産基盤整備を積極的に推進し、大型機械導入による労働生産性の向上を可能にした。また、整備面に併せて優良牧草の導入を図ることにより牧草の質と生産性が向上し、牧養力が1ha当り1頭から3頭へと向上した。このように肉用牛の集約生産が可能となったことにより、若者がUターン、新規就農する例が増え、地域の活性化にも大いに役立っている。例えば、黒島では平成元年からの10年間に15名が帰島し、肉用牛経営に参加している。

清浄牧野“ダニ”の侵入を許したらたいへんだ
| (3) | 家畜衛生・飼養管理、家畜改良、経営管理の指導支援 |
家畜伝染病予防事業、家畜衛生指導事業の推進および飼養管理指導により疾病の発生予防、損耗防止が図られ、ひいては肉用牛の生産性、育成率向上に寄与している。
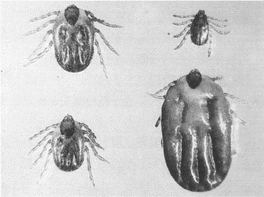
オウシマダニ |

1匹のダニがあっという間に牛や牧野を汚染する |

牧野における幼ダニ生息状況
また、表5・6・7のとおり、優良種畜の導入、人工授精普及推進および肉用牛群改良基地育成事業等の積極的な推進により、増体能力の向上および肉質の改善が図られている。
さらに、畜産会と連携した畜産経営技術高度化促進事業の展開により、肉用牛経営の改善が図られている。
| (4) | 肉用牛経営の規模拡大 |
家畜防疫衛生対策事業および飼料基盤整備事業等の生産振興事業の推進により、表8のとおり肉用牛経営の規模拡大が着実に進展し、1戸当り飼養頭数が昭和47年の5.7頭に対し、平成元年には22.1頭、平成10年には37.6頭と26年間で6.6倍となった。
| (5) | 地域総頭数の増加 |
八重山地域の肉用牛総頭数は、表8にも示しているとおり、昭和47年の7561頭に対し平成元年には1万5678頭、平成10年には3万6140頭と県全体飼養頭数7万8660頭の46%を占め、26年間で4.8倍の増となっている。なかでも、石垣島は6.1倍、小浜島5.3倍、波照間島および新城島では5.1倍と頭数増加が著しい。
| (6) | 産地の競争力強化 |
八重山地域の子牛取引頭数は、表9のとおり昭和61年3055頭、平成元年3839頭、平成10年には8271頭と着実に増加し、12年間に2.7倍となっている。
また、平成10年の取引頭数は、県全体取引頭数の40.3%を占めている。
子牛価格は堅実に推移しているものの、県内9市場平均よりやや低い傾向にある。これは、黒島および与那国市場の離島のさらに離島という厳しい条件を反映しているものと思われる。
支援指導活動のおもな内容や取組み成果を簡単にまとめると、表10のとおりである。
3.指導支援活動の波及効果の可能性
| (1) | 八重山地域内でダニ撲滅に向けた重点地域を定め、順次、その重点地域を移して全地域においてその目標を達成することができた。この過程で、最初の重点地域の経験やノウハウが効果的に活用された。 | ||
| (2) | また、沖繩におけるダニと九州・本州等におけるダニとは、生態・生理が異なっており、八重山地域におけるダニ駆除の技術が、そのまま適用の可能性をもつわけではないが、その経験やノウハウについては、他地域にも有効な先行事例となる可能性は大きい。 | ||
| (3) | さらに、八重山地域では放牧が重要な地位を占めており、その経験を九州・本州等において、今後の放牧が部分的あるいは全面的に導入が行われる場合、有効な情報源になることがじゅうぶん想定できる。 | ||
| (4) | 八重山家畜保健衛生所の業務体制と所掌事務内容は、九州、本州等における家畜保健衛生所の場合と異なるが、八重山家畜保健衛生所の以上の取組みと成果は、他地域の家畜保健衛生所に少なからぬ刺激とヒントを提供することもじゅうぶん期待できる。 | ||
| (5) | 八重山地域において、オウシマダニ撲滅に挑んだ経験とノウハウは世界各地のオウシマダニ撲滅に向けて大いに指針になり得るものと思われる。 |
4.今後の指導支援の方向・課題等
オウシマダニ撲滅を達成したので、今後は侵入防止対策に万全を期していかなければならない。また、外部寄生虫のハエ、蚊等の駆除、または内部寄生虫の線虫類などを含めた総合的な牧野衛生対策が課題である。さらに、草地等の基盤整備、改良増殖、飼養管理および経営指導等の生産振興面に対するきめ細かい支援指導が必要である。
併せて、八重山地域はわが国の最南端に位置しているため、海外からの疾病侵入防止および発生予察についても重点的に取組む必要がある。
| (8) | 八重山地域はわが国の最南端に位置しているため、海外からの口蹄疫や悪性伝染病の侵入防止、および発生予察について重点的に対策を確立していかなければならない。 |