畜産農家を核として農業者と消費者との連携による地域農業の振興
鈴木 宗雄
◎最優秀賞:地域振興部門福岡県 有限会社 一番田舎(いちばんでんしゃ) |
1.地域振興活動の内容
有限会社一番田舎は、平成6年に肉牛農家長浦牧場が中心となって、地域農業者たちが建設した農村と都市を結ぶ交流施設である。 「一番田舎」は、今日の農業情勢が大きく変化するなかで、農畜産物の価格低迷や多様化する消費者ニーズへの対応、また、農業・農村の果たす役割などの理解と啓発を図るため、農業体験や土や自然に親しんでもらう「ふれあいファーム」と、自ら生産した牛肉や地域のこだわり農産物、特産物を直売する「糸島農畜産物即売所」から構成されており、新たな農業・農村の活性化に貢献している。

実績を発表する筆者
1) 「一番田舎」の概要
この「一番田舎」は、表1にも示めすような概要、施設の他、駐車場等を含めて総面積は約9100㎡であり、舎長のほか舎員10名とパート5名で運営されている。
|
|
|
| 名 称 | |
| 有限会社「一番田舎」 | |
| 区 分 | |
| ふれあいファーム | |
| 糸島農畜産物即売所 | |
| 設置主体 | |
| 前原ふれあいファーム実行組合
(組合長 鈴木宗雄) |
|
| 長浦牧場
(代表 鈴木宗雄) |
|
| キャッチフレーズ | |
| ふれあいファームで元気再発見 | |
| 糸島農畜産物をあなたの食卓に | |
| 施設整備内容 | |
| 市民農園・体験農園・交流研修室
・ふれあい広場・フラワー園・ハーブ園・利便施設 |
|
| 直売所・食材加工室・管理室 | |
2) 「一番田舎」の基本方針
- 3) 「一番田舎」の現状
| (2) | 「一番田舎」は、農業や農産物を一方的に売ったりみせつけるのではなく、都市住民(消費者)と農村(生産者)がいろいろな情報を交換し、コミュニケーションを図ることによって、安全で質の高い農産物の生産に反映させる役割を図っていく。 |
| (3) | 「一番田舎」は、豊かな情報の交換や市民のよりどころとして、人が集まることにより、生産者や消費者の意識に刺激をもたらし、農業・農村の活性化と新たな食文化形成のシンボル施設とする。 |
100万都市の福岡市に隣接する人口6万人の前原市は、JRと地下鉄の相互乗入れなどで都心まで30分と交通の便も良く、また、九州大学の移転計画もあることから人口が急速に増加している。このような地の利を生かし、都市と農村の交流を通じて、問題山積みの農業を再生しようという構想で出発した「一番田舎」は、市民農園・体験農園として、都市生活者が安全で栄養豊かな野菜を生産・収穫する喜びを味わい、自然との触合いや健康保持、生き甲斐、コミュニケーションの場として評価があがっている。
糸島農畜産物即売所では良質、安全、新鮮、なおかつ安いということが、多くの「一番田舎」ファンをつくり、入場者数は平成6年の開場当初15万人であったものが、平成10年には25万人となり、また、農畜産物出荷者も50人から420人となり、販売額は3億円から現在は4億円を超えている。貸し農園の利用者も36名から区画いっぱいの80名となっているが、それでも希望者が多く順番待ちの状況である。

貸し農園は、地元はもとより近隣市町からの利用者も多く順番待ちの状況
「一番田舎」の入場者、農畜産物出荷者、売上高、貸し農園利用者の推移は図1、図2、図3、図4のとおりである。
2.地域の概況
前原市は福岡県の西端、糸島地方の東南部に位置し、東は福岡市に接し、山間地から平坦地までの地形を有し、東西12.5㎞、南北13.6Km、面積は104.5km2である。地質は花崗岩質である。気候は対馬暖流の影響を受けて温暖で、年間平均気温15.8゚C、年間降雨量は1600mmなっている。耕地面積は2203haで、圃場整備率は87%と高く、水田面積率は89%である。総農家戸数は1543戸であり、そのうち専業農家306戸、認定農業者169名で、農業は米、畜産、野菜、花も大型産地を形成しており、平成9年の農業粗生産額は91億1000万円で、作目別にみると、米19億円、野菜21億1000万円、花き19億3000万円、乳用牛11億5000万円、養豚9億円、養鶏5億1000万円、肉用牛2億8000万円となっており、畜産部門の生産概要は表2に示めすとおりで、粗生産額は28億5000万円で県内1位の順位となっている。
3.地域振興活動の内容
1) 活動のはじまり有限会社「一番田舎」代表の私は、自己の肉牛経営(長浦牧場)において、黒毛和種の大規模一貫経営を実施している。長浦牧場は当初、乳用雄子牛の肥育経営を行っていたが、輸入畜産物が年々増加していくなかで、量から質への経営転換を図るため、黒毛和種の繁殖・肥育の一貫経営に切替えるとともに、優良種雄牛「豊喜号」を導入するなど、表3のとおり常に将来を見越した計画的な経営を実施してきた。
また、私はJA糸島の肥育牛部会長として、「糸島牛」を銘柄牛化するなど地域リーダーとしても貢献してきた。
しかしながら、農畜産物の自由化に続く米の部分開放が決まり、農業の先行きに厳しさが増すなかで、農業後継者が農業をやっていける環境作りをしようと、変化の波を真っ正面から受けながらも攻めの姿勢で取組み、長浦牧場が推進母体となって、地域農業者と提携した「一番田舎」構想がだされた。
この構想は、今まで農家は生産のことのみ考えてきたが、これからは生産から販売まで農家側でやっていくことを理念としている。
この構想に前原市も連携し、ソフト部分で全面的に支援していくこととなった。
2) 活動の位置づけ
有限会社「一番田舎」が所在する前原市は、都市近郊農業地域として発展してきたが、平成4年の市制施行とともに急速に都市化が進んでいる。
このような状況のなかで、前原市では農業振興の目標を、
| (1) | 都市近郊の有利性を生かし、大きな変革と特色ある農業の展開により、食と農の共生関係を築く。 | ||
| (2) | 都市と農村が、また、消費者・都市生活者と農業者が相互に信頼、協調、補完しあう共生関係を築く。 |
としており、この目標にいち早く取組む体制を整えたのが「一番田舎」である。
「一番田舎」の取組む姿勢として、「私たち農業・農村大好き人間は、緑豊かな自然環境を生かし、あなたの健康の真んなかに心身のリフレッシュの場、そして糸島農畜産物を自信を持ってお届けするために、輝く汗をだしながら、都市と農村(消費者と生産者)の交流を図っていく」としている。このことが「一番田舎」のなかで形として現れており、それが都市生活者の評価を受け、ファンが増えている。
こうした「一番田舎」の取組みが地域農家への刺激となり、前原市の農業、農村において、これまでの生産者から農業経営者への意識改革や、流通販売の改善、触合い農業の展開、農産物のブランド化など、あらゆる面で新たな農業の展開が行われるようになった。
3) 活動の実施体制
有限会社「一番田舎」は、長浦牧場代表の私とその共同経営者で水稲も作る宮本剛氏、および野菜を栽培する藤野宗氏の3名で作る「前原ふれあいファーム実行組合」と、長浦牧場の2組織から構成され、それぞれが機能を分担し、代表は私である。
「一番田舎」は、このように農業者のみで組織され、運営されているものであるが、前原市の支援組織「前原市農力開発推進機構」や関連組織「いとのくに田んぼの夢倶楽部」や「前原市ふれあい農業ネットワーク会議」の支援・協力の力も大きいものがある。支援組織、連携組織の役割は図5のとおりである。
| (1) | 前原市農力開発推進機構:前原市が行う産・官・学による前原市の農力の開発と、新しい農業の展開を実践指導する推進機構であり、「一番田舎」は、この支援を受け運営企画を行っている。 | ||
| (2) | いとのくに田んぼの夢倶楽部:都市住民を会員(現在870名)として、前原の農業・農村情報を提供しており、これを通じ「一番田舎」の情報も送られている。 | ||
| (3) | 前原市ふれあい農業ネットワーク会議:農産物直売所、市民農園や観光農業などを行うグループが手をつなぐネットワークであり、「一番田舎」も、この会員で都市生活者の受入れ体制作りのための相互研修を行っている。 | ||
| (4) | 運営企画会議:「一番田舎」のスタッフと前原市農政課で定例会議を行い、農畜産物販売参加農家の研修も行う。 |
また、一番田舎が補助事業等の活用状況は表4に示めした。
4) 具体的な活動の内容と成果
| (1) | 有限会社「一番田舎」の推進母体である長浦牧場は、黒毛和種の大規模一貫経営の実現はできたものの、「一番田舎」に相当の投資を行うことに多少の不安はあった。特に販売の核となる自らが生産した牛肉を売ることは、安い輸入牛肉が出回るなかで、消費者に受入れてもらえるかどうか、また、地域農家にとっても自分たちの農畜産物が、本当に売れるのかどうかの疑問を持ちながらの出発であった。 | |
| (2) | しかしながら、牛肉については、長浦牧場が出荷した牛肉を食肉センターからブロックで引取り、1年間研修を受けたスタッフが製品加工を行い、一度食べると「究極の肉を追求し、きめ細かく柔らかく、ほど良い脂肪がのっている糸島牛」として、口コミで消費者が増え、リピーターとなる客がたくさんでてきた。 | |
| (3) | 野菜、花、加工品等を出荷する耕種農家も、長浦牧場の「万能堆肥」を利用した有機農産物として販売が好調に続くなかで、出荷品に自分の名前と自分が付けた価格を表示することにより良質、安全、新鮮、なおかつ安くという理念のもとに、生産・販売に力を入れるようになった。 |

万能堆肥を利用した新鮮な野菜や花の即売所

一番田舎では長浦牧場で生産された銘柄牛の「糸島牛」が直売されている
| (4) | このことは、「一番田舎」代表の私が、連日連夜の農畜産物出荷者との対話、圃場巡回等を行い、消費者のニーズを伝えながら、より良いものを作っていこう、と激励しながら一体となって取組んだ成果と思われる。
こうしたことが消費者のニーズにマッチし、生産者と消費者の信頼関係ができあがったといえる。 |
|
| (5) | 出荷者も努力したものは販売額となって表れ、多品目、生産増に力を入れ多い人は月に50~60万円の売上げになり、「一番田舎」登録農家も当初の約10倍の420名となり、畜産のみならず地域農業活性化の拠点となっている。 | |
| (6) | 貸し農園も、地元前原市はもとより福岡市など近隣市町からの利用者も多く、専門家による栽培指導や「万能堆肥」の無料提供もあり、利用者は持続的に利用するので、空きが少なく順番待ちの状況である。 | |
| (7) | 「一番田舎」が都市と農村の交流の拠点となった成果は、「一番田舎」が「このまま農業・農村を衰退させないぞ」という、強い意気込みで企画運営されている結果と思われる。 |
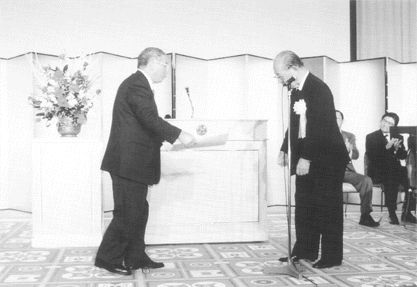
(社)中央畜産会桧垣徳太郎副会長より平成11年度地域振興部門で最優秀賞を授与される
| (8) | また、大規模な都市と農村の交流施設は、一般的には行政やJAが設置主体となって行われる場合が多いが、このように地元農家だけで組織・運営されている「一番田舎」は、関係者の並々ならぬ努力に負うところが大きく、功績として評価できる。 |

受賞祝賀会で夫妻揃って挨拶する筆者
5) 地域振興の活動の年次別推移
次に一番田舎の推進母体である長浦牧場と一番田舎のあゆみは表5のとおりである。
4.地域振興活動の波及効果の可能性
近年、都市近郊では農畜産物直売所が随所にみられるようになり、その売上高も大幅増となっているが、都市部に住む消費者には自然が豊かな農山村への期待やあこがれ、また、新鮮・良質・安価な農畜産物の供給が直売所の人気に結びついている。前原市における直売所等の触合い農業による販売額は6億6000万円で、前原市の農業粗生産額91億1000万円の7.3%を占めるようになっている。今までサブ的な流通だった直売所が、正規の流通にも影響を及ぼしはじめており、「一番田舎」がその牽引役を果たしているともいえる。
市場性を持たず、共販にも参加できなかった自給農業が、新鮮な農畜産物の提供をはじめ消費者との交流を通じて、ゼロから億単位の新たな市場を生み、社会性を獲得しはじめたとも考えられる。
地場での生産と消費を高めることは、やがて地域の自給度を高めていく。「一番田舎」はこのように隣合う農家と消費者が支え合う農業が、地域を再生するカギとなることを実証した事例である。
「一番田舎」の成功は関係者のたゆまぬ努力はもちろんであるが、
| (1) | 畜産農家と耕種農家が、畜産堆肥を介して生産から流通まで緊密な連携が取れたこと、 | ||
| (2) | 消費者が集まりやすいように、貸し農園など触合い施設が併設されていること、 | ||
| (3) | JAや行政との連携が緊密に保たれていること、 |
などが成功の要因として考えられる。
「一番田舎」の推進母体である長浦牧場は、(社)中央畜産会の平成8年度ゆたかな畜産の里推進事業に参加して、畜産局長賞を受賞した農事組合法人「前原市畜産経営環境保全組合」の組合員でもあるので、その事業のなかで「一番田舎」のことが紹介されている。また、「一番田舎」は(社)中央畜産会の平成7年度特色ある地域畜産の創造・体験交流促進事業のなかでも先進事例として紹介された。
このようなことから、「一番田舎」には九州各県はもとより、西日本地域の農業関係者等の見学者も多く、また、「一番田舎」代表の私もあちこちから講演に招かれることが多い。
そのようなときは、いつも「守りではなく、攻めの農業を」「若者が進んで取組める農業を構築しよう」と説いている。
このように、「一番田舎」関係者の農業に対する限りない愛情と熱意ある行動が、今日の成功を導いたものとも思われる。
5.今後の活動の方向・課題等
「一番田舎」が、今後も地域農業振興の拠点となっていくためには、関係者全員が消費者ニーズを的確にとらえた生産体制の維持、およびサービスの提供に応えるための人材育成が重要な課題である。前原市では市の農業振興の柱として、次の3点を重点施策としている。
| (1) | 人材育成対策:今日の農業をめぐる情勢は、市場原理を取入れたものになっており、農業経営者としての意識改革と勉強により、経営感覚に優れた人材育成を支援する。 | |||
| (2) | 生産と流通販売対策:これからの農業は、生産のことだけ考えるのではなく、農家側で生産から流通・販売までを行う取組みが必要でこれを推進する。 | |||
| (3) | 都市と農村の共生対策:食料生産と環境保全を農業・農村が果たしている役割など、都市生活者に理解してもらいながら食と農、都市と農村の共存・共生を推進する。 |
こうした前原市の農業振興施策と「一番田舎」は一致した活動を展開しており、今後の地域農政推進のうえからも大きな期待が寄せられている。