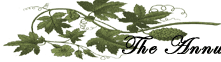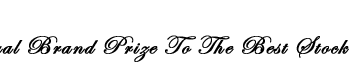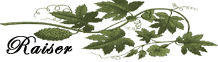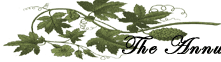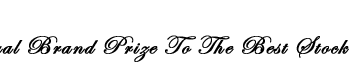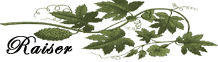|
中央全体審査委員会と各部門の中央審査委員会を代表して、審査の結果と「畜産大賞」選考の経過について報告申し上げます。 今年度審査の対象となった出品事例は、経営部門9事例、地域畜産振興部門21事例、研究開発部門18事例であり、それらを合わせると「畜産大賞」の選考対象は48事例になります。今年度から新たにこれまでの「推薦公募方式」に加えて「一般公募方式」を取り入れたこともあって、昨年度に比べると選考対象は12事例ほど増えました。
選考の結果は、別掲の通り、畜産大賞は地域畜産振興部門で最優秀賞を受賞した岩手県の葛巻町畜産開発公社で、「限られた地域資源を最大限に生かし東北一の酪農の町に―公社を核とした地域支援の実践―」
事例であります。
最優秀賞は経営部門が岡山県の石賀博和さん・石賀恵子さん夫妻による「地域資源を生かした低コスト肉用牛繁殖経営」
、研究開発部門はフィールド方式の肉用牛改良システム開発グループによる「フィールド方式による産肉性の育種価評価とその利用体系の開発」であります。
これらの受賞事例の具体的な内容については、この後行われる業績発表において受賞された方々から詳細報告されることになっておりますので、私からはそれぞれの事例の概要と評価の根拠となった特徴点を中心に紹介をしたいと思います。
まず、畜産大賞を受賞しました葛巻町畜産開発公社の活動についてです。
葛巻町畜産開発公社は、昭和51年に葛巻町・葛巻町農協(現在の新岩手農協)・葛巻財産区の三者の出資によって設立されました、いわゆる公共育成牧場を運営・管理する組織であります。
昭和50年度から57年度にかけて北上山系開発の一環として実施された、広域農業開発事業によって造成された1100haの草地を基盤に、地域内の酪農家を対象にした育成牛の夏期預託放牧、周年預託による初妊牛の育成・供給、乾草を主とした粗飼料供給、搾乳牧場の経営による飼養管理技術、草地の維持管理技術等の展示・普及を目的として発足したものです。
その後、時代の変化に対応して順次事業内容を拡大し、現在は、発足当初からの事業に加えて、展示・普及を目的とした生乳処理・加工施設による飲用乳、アイスクリーム、ヨーグルト、チーズなどの製造・販売、牧場内に設置されたレストハウス、宿泊施設などを利用した都市住民とのふれあい交流事業、さらに草地周辺の山林を活用したしいたけ栽培などの林産事業などを行っています。
この事例が、今回「畜産大賞」に値するとして評価された点は、多くの公共育成牧場が牧場自体の経営維持に困難を抱えている状況の下で、ここでは立派に地域内の酪農の振興に寄与していることに加えて、葛巻町のほかの第3セクターと連携し、町が目指す「ミルクとワインとクリーンエネルギーのまち」づくりに中心的な役割を果たしていることであります。
この地域は、畜産開発公社が設立されるまでは、「日本のチベット」とまでいわれた山間へき地でありましたが、今では2万人近くに及ぶ牧場体験学習参加者を含めて年間に30万人が集う文字通り東北一の酪農の町に発展しています。
評価された点の第1は、地域の酪農振興に寄与した支援活動であります。公共育成牧場が通常行う育成牛の預託放牧などの活動に加えて、当時はまだ経験の浅かった草地の維持管理・利用技術についての実証展示、標高の高い圃場での牧草との輪作によるデントコーンの栽培方式の確立・普及、中古電柱その他の廃材やビニールハウス、パイプハウスなどを利用した低コスト牛舎・施設の展示・普及、さらには、経営危機に陥った酪農家に対する初妊牛の無償供与など、地域内の酪農振興に有効・適切な多様な活動を展開してきたことです。
評価されたことの第2点は、公共育成牧場の運営に当たっての経営姿勢であります。発足当初から、いわゆる「親方日の丸」的な意識を排除し、職員全員に経営者的感覚と経営者的意識の徹底を図って低コスト経営に努め、長期にわたって安定した収支バランスを維持してきていることです。
徹底した保守点検・整備を行うことによって当初導入した機械・施設をいまだに稼動させているとか、古電柱その他の廃材、ビニールハウスやパイプハウスなどを活用した牛舎やカウハッチを開発するなど、投資を抑制し費用節減を基本とした経営姿勢が、自らの経営を安定させると同時に地域内酪農家への実証展示の役割を果たすことを可能にしています。
いわば、経営者的感覚、経営者的意識を持つことが公企業である公社と私企業である農家酪農を共通の基盤に立たせ、両者を結ぶ絆(きずな)をつくり出しているといえます。
評価されたことの第3点は、あるのは山だけといわれるような山間へき地の地域おこしに中核的な役割を果たしていることであります。夏の「くずまき高原牧場まつり」とか冬の「スノーワンダーランド」といったイベントのほか、牧場体験学習など日帰り・滞在を含めて年間30万人に及ぶ人たちに足を運ばせることによって、葛巻町の自然と自然が生み出した農・畜・林産物の宣伝に大きく寄与しています。
葛巻町が打ち出している「ミルクとワインとクリーンエネルギーのまち」づくりに応えて、家畜ふん尿によるバイオガス発電にも着手しており、将来は牧場内における風力発電を加えて電力自給のエコファームを目指しています。
現在、畜産開発公社はこれまでの経営実績を評価されて県内他地域の公共牧場の管理も委託されており、また、東北、関東などの他県からも多くの初妊牛預託育成の依頼があり、それを受け入れています。今では地域内酪農振興の枠を越えて、日本の酪農の維持・発展に寄与する役割を担うに至っています。
以上、紹介したような経営姿勢とそれに基づく諸活動が、公共牧場として担うべき指導支援・地域振興活動に一つの方向を示すものとして、「畜産大賞」に値すると評価しました。
続いて、その他の部門の最優秀賞受賞事例についてであります。経営部門の石賀博和さん・石賀恵子さん夫妻の肉用牛繁殖経営は、岡山県の北端に位置する蒜山山ろくに広がる盆地の南端にあって、山あいが迫る山間地域に立地しています。
今春から予定されている長男が就農しますと労働力は3人になりますが、現在は夫妻2人で成雌牛を約60頭飼養しています。
昭和50年に博和さんが短大卒業と同時に就農し、それまでの稲作・タバコ作・成雌牛2頭の肉用牛に加えて、一時期リンドウ栽培を取り入れたこともありましたが、昭和60年代に入って肉用牛と稲作の2つの部門に単純化し、平成12年に現状規模に達したところで稲作を止めて肉用牛専門経営に転換しました。
この経営の優れていると思われる点は、何といっても徹底的な省力化と各種技術の改善によって、子牛生産コストの大幅な節減と極めて高い労働収益を実現していることであります。
飼養牛を生後4ヵ月齢未満の子付き成雌牛群、受胎確認済妊娠牛群、育成牛群の3群に分け、子付き成雌牛群はつなぎ牛舎で個体別管理をすることによって受胎率の向上と子牛の初期管理の徹底を図り、妊娠牛群と育成牛群は夏期間昼夜放牧を取り入れた群飼育で省力化を図っています。さらに、採草利用の飼料生産はロールベール方式を導入することによって省力生産を実現しています。
優れていると思われる点の2つ目は、出荷後の子牛の肥育成績を独自に収集し、胚移植技術を活用して育種価の高い成雌牛をそろえることによって牛群改良を図っていることであります。
県内育種価評価基準に照らしてAランク以上の牛が、飼養している成雌牛の60%近くを占めており、10%程度にとどまっている県平均を大きく上回っています。
さらに、3つ目の優れていると思われる点は、異種部門間の連携を進めることによって地域畜産の振興に寄与していることであります。地域の肉用牛経営との連携はいうまでもないことですが、畜種の違いを越えて周辺の酪農経営と連携を図り、施設や機械などの技術的な情報交流に加えて、削蹄や畜舎修理などの共同作業を行っています。
酪農にしても、肉用牛経営にしても点在化してきている状況を考えると、畜種の違いを超えた連携は、大きな意味を持つものといえます。
最後に、この経営の特徴を示す経営成績を紹介すると、成雌牛1頭当たり年間労働時間35.5時間(1日8時間に換算して4.4日)、子牛1頭当たり生産原価18万7538円、成雌牛1頭当たり年間所得20万2335円であり、8時間換算投下労働1日当たりの所得に置き換えると4万5576円になります。いずれも、群を抜いた水準といえます。
次に、研究開発部門で最優秀賞を受賞しましたフィールド方式の肉用牛改良システム開発グループの研究開発事例についてであります。
この事例は京都大学と大分県と熊本県の関係者によって組織された研究グループによる黒毛和種と熊本系褐毛和種の枝肉成績の収集・解析から、それに基づく種雄牛の作出体系に至るまでのシステムの構築に関する研究成果であります。
研究内容は4つに分かれており、1つはフィールドデータの収集システムの確立、2つ目は繁殖雌牛および種雄牛の育種価評価技術の開発、3つ目は育種価評価情報普及システムの構築、4つ目が育種価情報に基づく種雄牛作出体系の構築であります。
いわば、どのようにデータを収集するか、収集されたデータをどのように解析し評価するか、その結果をどのように現場に伝えるか、その情報を受けてどのようにして種雄牛を作出するか、といった一連の体系の研究開発であります。
中心的な問題は育種価評価の方法であり、これには既に開発されたいくつかの方法がありますが、その中からBLUP法と呼ばれる方法を選んでわが国のような小規模農家から収集されたデータに基づく育種価評価にも有効かどうかを検討し、それをベースにわが国にも適用可能な独自の手法を開発しました。
大分県と熊本県においてはこのグループによって開発されたシステムに基づいて既に優秀な種雄牛が作出されており、産肉性に関する各要因の改善に大きく寄与しています。育種価評価技術は現在40道府県に導入されており、今後それぞれの道府県におけるデータの蓄積に応じてこのグループによって開発されたシステムが大きな意味を持ってくるものと推測されます。
以上、大賞と2つの部門の最優秀賞の受賞事例について、その概要と評価の根拠を説明させて頂きました。いずれの事例もそれぞれの部門において素晴らしい業績を上げ、大きな意義を持つ事例ばかりであります。
毎年度申し上げることですが、「大賞」はまったく異質な部門の最優秀賞の中から選ぶことになります。そこに審査上の大きな難しさがあるわけですが、日本畜産のおかれている現状と将来方向に照らして、大局的な観点から総合的な判断に基づいて、表彰することの意味合いを考えて選ばせて頂きました。
時間の関係で省略せざるを得ませんが、最優秀賞に至らなかった各部門の優秀賞および特別賞受賞事例、残念ながら選外となりました事例についても、それぞれの部門において優れた実績を持つ事例ばかりであります。
それらの事例を含めて、その内容が日本全国に広まることによって、いささかでもこの表彰事業が日本畜産の前進に寄与することができればと願っています。
なお、ひとこと付け加えさせて頂きますが、ここ数年「大賞」受賞事例はスケールの大きな事例が続いています。「大賞」、大きな「賞」であるからスケールの大きなものということでは決してありません。日本畜産の発展に寄与しうる事例に光を当てるのがこの事業の目的であります。スケールの大小にかかわりなく、多くの事例が積極的に応募されることを期待しております。
最後になりましたが、受賞されました皆様方に心からお祝いを申し上げますとともに、今後一層のご活躍をご期待申し上げまして、審査報告を終わらせて頂きます。
|