地域総合支援体制による中山間地域の肉用牛振興
島川 健次
◎畜産大賞最優秀賞:指導支援部門大分県久住町畜産センター |
1.指導支援業務の概要
大分県の畜産は、肉用牛を中心として酪農、養豚、養鶏の振興に行政・生産者団体が一体となって取組んでおり、なかでも肉用牛では、県の農業振興計画である「新農業プラン21」の5大プロジェクトの1つともなっている「大分県肉用牛10万頭プロジェクト」推進協議会を中心として、肉用牛の増頭を重点とする各般の振興施策を展開しているところである。このようななかで、久住町の畜産は、全国的にも希有な広大な草資源を活用し、放牧を取入れた夏山冬里方式の肉用牛経営が中心である。
昭和54年4月に、肉用牛飼養農家による自主的組織「久住町和牛振興会」(会員数557名)が発足するとともに、それまで町、同町農協がそれぞれ行っていた指導の一元化が強く求められるようになった。このため、昭和57年4月、町、農協、農業共済組合の3者で構成される第3セクター方式による総合指導機関「久住町畜産センター」が設立された。
現在、同町では、畜産に関するすべての業務が畜産センターを中心として行われており、なかでも肉用牛では、飼養頭数が順調に伸び、平成10年2月1日現在7090頭と県全体頭数の10.4%を占め、県内市町村のなかで、第1位の飼養頭数となっている。また、農業粗生産額に占める畜産の割合は56%(26億円)であり、肉用牛は全体の26.2%(12億1000万円)に達している。
これらの成果は、同センターの指導支援活動によるものであるといえる。
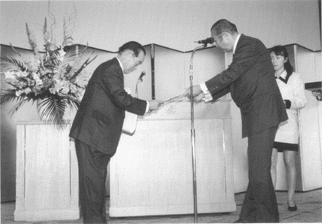
山中貞則中央畜産会長より大賞の授与を受ける左右田所長
2.指導支援の内容
- 1) 指導支援の対象
- (2) 畜種並びに戸数
- (3) 経営形態
- 肉用牛:稲作+野菜または椎茸の複合経営であり、肉用牛は広域農業開発等により管内では23ヵ所の共同牧場が開発・整備され、草地造成面積は955haであり、放牧・採草(乾草)利用が盛んに行われている。また、肥育経営は、農協の肥育センターが中心となって、管内の子牛価格の買い支えと併せて、枝肉データを生産者へフィードバックし、改良面に活用している。
- 酪農:畑作酪農で専業経営が中心である。管内には、ガンジー種を飼養した観光牧場があり、都市と農村の交流の場として、その一翼を担っている。
- 養豚:経営内一貫経営で米・野菜等の複合経営が中心である。
(1) 対象地域
久住町全域が指導対象地域になっている。
飼養畜種並びに飼養戸数は表1のとおりである。
|
|
|||
| 畜 種 | 戸 数 | 頭 数 | 1戸当り |
| 肉用牛 | 322戸 | 7,090頭 | 22.0頭 |
| 酪 農 | 13戸 | 500頭 | 38.5頭 |
| 養 豚 | 12戸 | 10,500頭 | 875.0頭 |
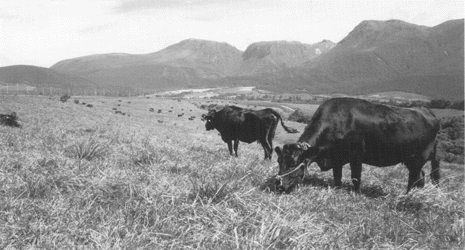
共同利用牧場の放牧風景
- 2) 指導支援の開始
昭和54年4月肉用牛飼養農家全戸が加入した、自主的組織である「久住町和牛振興会」の設立を契機として、それまでの町、農協による戸別の指導体制に代わり、一元化された総合指導組織の設置が強く要望されることになり、当時、隣接市町村ですでに設置されていた畜産センターをモデルとして、町の指導のもとに、町・農協・農業共済組合の3者による第3セクター方式で総合指導機関を設置することとなり、町が畜産センター設置条例を制定して、「久住町畜産センター」が昭和57年4月発足した。
同センターの土地・建物については、町が既存の物件を取得のうえ提供しており、運営費については町が3分の2、農協が3分の1を負担し、人件費については、構成機関の3者がそれぞれ人材を派遣し負担している。
同町には、県の畜産試験場(明治39年)があり、古くから肉用牛の育種、改良に対して熱心な土地柄で、当時、とくに育種・改良に卓越した手腕を発揮していた同試験場の次長が退職する機会をとらえ、センター所長として迎えた。同氏は、今日まで15年の長きにわたり活躍している。
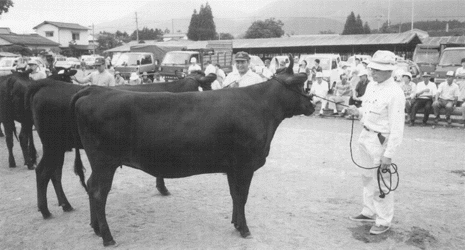
久住町畜産品評会の風景
同センター設置後は豊後牛の増頭を目標に掲げ、昭和63年に策定した、町独自の長期増頭計画目標である肉用牛繁殖雌牛3000頭(現在2714頭)の達成に向けて、県の肉用牛10万頭プロジェクトと連携した増頭運動を展開している。
また、肉質の向上による豊後牛の銘柄確立を目的として、育種・改良に積極的に取組み、優秀な種雄牛の造成および繁殖雌牛の保留を行っている。
このように、着実に実績が伸びた背景には、各機関からの派遣職員が優秀であるうえに、町長、農協組合長の指導力に加え、農家の信頼ある所長の人望と手腕によるところがきわめて大きく、その影響力は、74歳を超えた今でも、続投が望まれていることにも現われている。
- 3) 指導支援の実施体制
- 指導支援の実施体制は図1のとおりである。
4) 具体的な指導支援の内容と成果
- Ⅰ. 指導支援の内容
| 〈振興活動〉 | ||
| (1) | 増頭推進のため久住町和牛振興会の支部(畜産小組合=自治会単位)に推進会議を設置し、大分県肉用牛10万頭プロジェクト推進協議会と連携し、増頭推進を展開している。 | |
| (2) | 子牛市場事前指導:市場上場予定子牛の巡回指導を定期的に実施し、子牛市場性向上のための事前指導を実施している。 | |
| (3) | 削蹄・毛刈り講習会:削蹄・毛刈り講習会を年1回開催している。
その成果として、子牛市場性の向上・斉一化がはかられている。 |
|
| (4) | サイレージコンクールの開催:良質なサイレージを作るための調整技術を向上させるため、サイレージコンクールを年1回開催し、優秀者を表彰し啓発をはかっている。 | |
| (5) | 小組合長研修:小組合長の連携強化および先進技術の研修と親睦を目的として、年1回先進地研修を開催している。 | |
| 〈改良活動〉 | ||
| (1) | 地区品評会の開催:県内ではほとんど実施されていない地区品評会(旧町村単位=3地区)を農協と共催で開催している。その効果として生産者レベルでの飼養管理技術・改良技術の向上により、基礎雌牛群のレベルアップ・子牛市場性の向上がはかられ、増頭意欲が非常に盛りあがりをみせている。 | |
| (2) | 品評会・共進会における出品牛の巡回指導:地区品評会選抜牛・町品評会選抜牛・郡市共進会選抜牛について戸別巡回し、育成状況等について指導を行っている。
その成果として、平成8年大分県畜産共進会において、農林水産大臣賞(グランドチャンピオン賞)を受賞している。 また、第7回全国和牛能力共進会では、町内産子牛が、第3区(若雄の部)で農林水産大臣賞を受賞。加えて第9区(高等登録群)でも優等賞を受賞するなど確実に実績をあげている。 |
|
| (3) | 育成管理指導:優秀な血統の繁殖雌牛については、地域内で保留するように指導を行い、育成管理技術について飼養管理技術の指導を定期的に実施している。
その成果として、日本一の種雄牛である「糸福号」の産子牛約900頭の優秀雌牛を町内で保留している。 |
|
| 〈研修広報活動〉 | ||
| (1) | 座談会の開催:和牛振興会の会員(夫婦同伴)を対象に、小組合ごとに畜産における総合的指導および親睦会を年1回実施している。 | |
| (2) | 広報誌の発刊:「久住町和牛振興会だより」を年2回発刊している。 | |
| (3) | 研修会の開催:和牛振興会会員を対象に、県畜産試験場で視察研修を実施している。
その成果として、各種啓発活動により増頭意欲の向上がはかられている。 |
|
| 〈青年部活動〉 | ||
| 後継者グループ(はなぐり会)による各種行事の計画立案実施。
最近の取組みとして、平成10年3月に優良種雄牛の造成と肉用牛の品種改良および卓越した飼養管理技術を習得することを目的とした、中核農家で構成される自主的組織「久住New Wind」の結成を指導した。 |
||
| 〈婦人部活動〉 | ||
| 畜産経営感覚の向上のため、外部より講師を招聘し経営講座を開催するなど、積極的な活動を展開しており、その成果として、(社)中央畜産会の主催する「全国優良畜産経営管理技術発表会」で畜産局長賞を受賞した。 | ||
| 〈その他の活動〉 | ||
| (1) | 豊後牛ヘルパー事業への取組み:平成8年度に久住町肉用牛ヘルパー推進協議会を設立し、県単独事業である「豊後牛ヘルパー事業」にいち早く取組み、ヘルパー要員については、小組合長が各地区にて人選を行い、協議会へ推薦しヘルパー要員の登録を行っている。 | |
| (2) | 各種表彰:久住町和牛振興会の総会において、年間多頭増頭者表彰・優秀畜産小組合表彰・特別表彰・功労者表彰・新規飼養農家表彰・サイレージコンクール優秀者表彰を行い、飼養管理技術の高位平準化とともに意識の高揚をはかっている。 | |
- Ⅱ. 指導支援の成果
| (1) | 平成8年から確実に増頭:県内で唯一着実に増頭している地域であり、飼養頭数は県全体の約10%を占めている。また、肉用牛飼養農家戸数の減少率も、他地域と比較して低い。 | |
| (2) | 子牛価格の上昇:放牧地域にみられがちな子牛の発育遅延があったが、根強い指導の結果、本年8月には、町内の市場価格の平均が、豊肥市場の平均価格をはじめて上回った。 |
- Ⅲ. 成果をあげたポイント
| (1) | 現地巡回指導等を繰返し実施したこと。 | |
| (2) | 補助事業の継続による生産基盤整備:現場から寄せられた要望に沿って幅広く各般の補助事業を安定的に実施している。
平成9年度は28事業(事業費ベースで1億6200万円)を実施した。 |
- 5) 指導支援活動の年次別推移
- 指導支援の年次別活動状況は表2のとおりである。
3.指導支援活動の波及効果の可能性
| 1) | 県内では、早くから町・農協が一体となった指導支援の一元化がはかられているが、機構・生産者との連携・人事・職員の身分保障等(町・農協の待遇の違い)必ずしもうまくいってない。 | ||
| 2) | 当久住町の場合は、生産者組織である和牛振興会を母体として、生産者と一体となった指導支援活動を行っており、派遣職員についても町・農協の優秀な職員を派遣するなど、地域ぐるみの取組みが今日の成果をあげたものと思われる。 | ||
| 3) | このような、組織体制を整備する場合は、ややもすると体裁にとらわれがちであるが、要は生産者のニーズに如何に応えるかであり、そのためにそれぞれの組織がどのような支援体制を講じるかがポイントとなる。 |
久住町では、センター所長が優秀な人材であることはもちろんのこと、町・農協の物心両面にわたる支援のたまものにほかならない。
4.今後の指導支援の方向・課題
久住町畜産センターが設立して、本年で16年目を迎え、長期増頭計画に基づいた肉用牛の増頭・銘柄確立・低コスト生産を支援指導の柱として、積極的に取組んできた。近年、社会・経済状況の変化にともない、農業情勢も変革期で当町も例外なく、高齢化・後継者不足・過疎化が進展するなかで、和牛振興会の青年部を中心として、規模拡大意欲が高まっており、着実な増頭がはかられている。

乾草収穫作業
しかしながら、21世紀に生き残る肉用牛経営を確立する課題も数多く残されており、今後は全国的にも恵まれた自然と共生しながら、豊富な草資源を有効活用した低コスト生産をめざし、次世代にバトンタッチできる「儲かる肉用牛経営」の確立が必要である。
また、農業のもつ多面的な機能を生かし、国土保全・地球にやさしい環境づくりなど農業サイドだけでなく、町全体として都市との交流の場として、積極的に「町おこし」に取組む必要がある。
なお、久住町畜産センターの構成員であった久住町農協が、平成10年4月1日に近隣の1市2町の農協合併により、「JA大分みどり」となったが、久住町畜産センターはそのまま存続することとなっており、農協合併による機構改革が、業務に影響を与えないように努めている。本年は、5年に1度の和牛振興大会の開催年でもあり、肉用牛の増頭目標である成牛3000頭の達成に向けて、さらに努力することとしている。