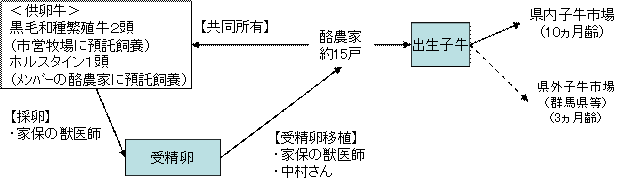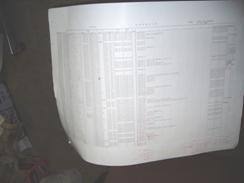|
活動・取組み内容の調査報告 |
|
新潟県・中村日出男経営(酪農) |
|
|
|
中村さんの経営は、「フリーストール体系の導入と転作田の活用による酪農専業経営の確立」というタイトルで平成12年度全国優良畜産経営管理技術発表会に出品された優良事例であり、(社)中央畜産会と(社)秋田県農業公社が平成19年2月に開催した『平成18年度優秀畜産表彰中央情報交流会(秋田開催)』において話題提供いただいた事例である。
|
Ⅰ 取り組みの概要(現在)
<経営の概況(平成19年1月現在)>
経産牛64頭(搾乳牛49頭)、育成牛40頭、労働力2人(経営主、妻)
年間産乳量8,600~8,800kg、乳脂率3.59%
分娩間隔13.9ヵ月、受精に要した種付回数2.0回
F1生産約4頭/年、粗飼料自給率約20%
<取り組みの特徴>
・平成3年にフリーストール・ミルキングパーラー搾乳体系を取り入れ、規模拡大と省力管理、
飼養牛の健康管理に努め、経営安定を図る
・とくに、PCを一般的に普及される前(いまから25~26年前)から導入し、牛群管理と経営管理を徹底
・飼料生産面については、転作田の積極的な活用と飼料畑の集積を実施し、経産牛1頭当たり18aを作付け
・近年は夫婦2人の労力による適切な経営を目指し、以前自ら行っていたTMR給与を購入発酵TMRに切りかえ、
購入飼料費と乳量の適正バランスの維持に努めている
・地域との連携面では、受精卵移植研究会、飼料イネ生産組合、特別栽培農家への資源循環の役割を担うほか、
小学生の体験受入れや農業高校生の実習場所提供を実施
Ⅱ 取り組みの内容(平成19年1月現在)
1 地域の概況
中村さんの経営のある新潟県長岡市三島地域(旧三島町)は、新潟県のほぼ中央に位置し、
美しい自然と歴史に恵まれた町である。町の起源は古く、上杉謙信以前より立派に集落を
形成しており、天明年間には脇野町に幕府の公領として代官所がおかれ、その支配下に
発展してきました。昭和30年3月、三島町脇野町と大津村の1町1村合併し三島町が誕生、
平成17年4月に長岡市と合併して今日に至っている。
三島地域は、地方中核都市長岡市に隣接することから、上越新幹線、関越自動車道等の
高速交通環境に恵まれた地域である。この地理的条件と、ほ場整備、農村総合モデル事業、
工業団地、宅地造成等の事業に積極的に取り組んできた結果、農業生産基盤及び環境整備、
電子部品先端産業の立地がなされ、人口増加が図られてきた。
地域の世帯数は2,152戸、人口は7,400人である(平成19年1月現在)。
2 経営の歩み
|
年次 |
作目構成 |
飼養頭数 |
経営および活動の推移 |
|
昭和28 昭和39 昭和45 昭和46
昭和48 昭和49 昭和50 昭和58 平成元 平成3
平成5
平成8
平成10 平成12 平成15 平成18 |
水稲、酪農 〃 〃 酪農
〃 〃 〃 〃 〃 〃
〃
〃
〃 〃 〃 〃 |
経産牛1 経産牛5 経産牛8 経産牛30
経産牛34 経産牛36
経産牛40
経産牛58
経産牛64 |
両親が経産牛1頭より酪農を開始(水稲1ha) バケットミルカーの購入 総合資金650万円を借り入れ、牛舎を新築移転 米の減反政策を機に、自己所有している水田4.5haすべてに飼料作物の栽培を行い、酪農専業経営に転換 サイロ1基(128m3)を設置、トウモロコシサイレージ調製開始 本人就農 サイロ2基(54m3)を増設 サイロ2基(54m3)を増設 畜産会の経営診断受診(2年継続) 経産牛1頭当たり乳量6,289kg 有限会社(資本金500万円)組織とする 旧牛舎の内部改造と増築により、フリーストール・ミルキングパーラー搾乳の体系とし、規模拡大を図る トウモロコシ栽培から牧草栽培に切り替え、 育成舎兼乾乳舎、堆肥舎を新築 代謝プロファイルテストを開始 ロールベーラ、ベールラッパを導入し、ロールラップサイレージ体系へ移行 育成舎、堆肥舎新築 地域の酪農家と連携し中越受精卵移植研究会を設立 自走式マニュアスプレッダを購入(個人)、共同散布 経産牛1頭当たり乳量8,800kg |
3.経営・生産の内容
(1)労働力の構成
|
区分 |
続柄 |
労働力員数 |
|
|
家 族 |
本 人 |
1.0 |
飼養管理全般、データ分析、飼料生産 |
|
妻 |
1.0 |
飼養管理全般 |
(2)土地所有と利用状況
|
区 分 |
実面積(a) |
|
畜産利用地面積 (a) |
備考 |
|
|
うち借地 |
|||||
|
耕 地 |
田 |
450 |
|
250 |
転作田、うち200aがH18夏の水害で損壊 |
|
畑 |
750 |
600 |
700 |
台地 |
|
|
樹園地 |
|
|
|
|
|
|
計 |
1,200 |
600 |
1,150 |
|
|
|
畜舎・運動場 |
80 |
- |
80 |
|
|
|
その他 |
山林 |
200 |
- |
- |
|
(3)施設等の所有状況
|
区分 |
形式 |
面積・数量 |
区分 |
形式 |
面積・数量 |
||
|
畜舎 |
成牛舎 |
木造平屋 |
18×10m |
機械
|
ミルキシングパーラー トラクター |
8頭シングル 2,100L 48ps
|
一式 2台 |
|
施設 |
堆肥舎 |
木造 |
7.2×7.2m |
||||
(4)技術等の概要
|
飼養品種 |
ホルスタイン種 |
|
飼養方式 |
フリーストール |
|
搾乳方式 |
ミルキングパーラー方式 |
|
牛群検定事業 |
参加 |
|
自家配合の実施 |
なし(以前は実施) |
|
食品副産物の利用 |
なし |
|
ET活用 |
あり |
|
F1生産 |
あり |
|
カーフハッチ飼養 |
なし |
|
採食を伴う放牧の実施 |
なし |
|
育成牧場の利用 |
なし |
|
ヘルパーの利用 |
あり |
|
コントラクターの活用 |
なし |
|
協業・共同作業の実施 |
飼料生産(飼料イネ)、ふん尿処理(水田へのたい肥散布) |
|
施設・機器具等の共同利用 |
なし |
|
肥育部門の実施 |
なし |
|
生産部門以外の取り組み |
食農・体験交流活動(ふれあい体験、乳搾り、牧場仕事体験等) |
4.経営管理技術や特色ある取り組みの内容
1)徹底的なデータ活用による飼養管理・牛群管理の実践
中村経営では、乳用牛群検定結果、JMR(妊娠遅延指数)診断のほか、血液検査による
代謝プロファイルテストを実施している。これらで得られるデータを活用し、種雄牛の選定、
飼料管理等の検討を行い、牛群改良と乳成分の向上に努めてきた。
(1)代謝プロイファイルテスト
①取り組みの概要
・平成5年ごろより実施
・年2回実施(平成18年は年3回実施)
・1回につき約20頭を実施、とくに分娩前後の具合の悪いものを優先的に分析
・分析結果は、共済組合、普及センター、開業獣医の3者とともに検討を実施
・分析料金2,000円/頭、ただし10,000円/回を上限としており安価
②取り組んだ背景
共済組合に誘われて開始した。共済組合としては事故率を抑えることが共済の発動の
減少につながることから推進先を探していた経過もある。このこともあり、共済組合の
十分な協力を得ての実施体制がとられている。
③成果等
・泌乳末期の過肥が減少。「種付の遅延→太る→繁殖障害の発生可能性高い」という
サイクルの牛が改善された。
・現在、長岡市内では酪農家8戸のうち4戸が受診するようになった。
④今後
・代謝プロファイルテストの分析結果を累積し、個体分析を行いたいと考えている。
(2)牛群検定データ
・育種改良、普段の飼養状況を把握するために利用している(量、乳質、体細胞)
・送付されてくる牛検帳票で1頭ごとにチェックしている。大家畜畜産経営データベース
については加入しており代行支援(普及センター)で送られてくるグラフを先述の
帳票でチェックした事項の再確認に使用している。
・最近はMUNを見ながらN含量なども検討している
2)転作田を利用した自給飼料生産
中村経営では米の生産調整に対応し、自家水田450a(現在は災害で200aのみ使用)を
全て飼料作物生産に活用するとともに、飼料畑の借地による集積を図り、自給飼料増産に
努めてきた。
また、地域内の集団転作田における飼料作物の栽培を飼料イネ生産を共同で実施している。
なお、地域の酪農家は周辺の酪農家は、全量を飼料購入している者が多い。
(1)飼料生産の状況
① 飼料作物の生産・利用状況
|
飼料作物名 |
実面積 (a) |
作付面積 (a) |
総収量 (t) |
作付 体系 |
利用形態 |
|
イタリアンライグラス |
900 |
900 |
5 |
1回刈 |
ラップ サイレージ |
|
スーダングラス(2回刈)、 ソルゴー(3回刈) ミレット(晩成種、1回刈) |
900 |
6 8 4 |
2回刈 3回刈 1回刈 |
||
|
混播牧草 |
50 |
50 |
|
|
|
|
計 |
950 |
1,850 |
|
|
|
② 労働投下
飼料生産は経営主(日出男さん)1人で実施
(2)地域と連携した飼料イネ生産(飼料イネ生産組合による生産の概要)
地域内の集団転作田において飼料作物を共同で作付け
|
①構成 |
地域の8人(耕種農家6人、酪農家2人)で結成 |
|
②設立 |
平成14年 |
|
③作業分担 |
栽培作業:耕種農家、収穫作業:酪農家 |
|
④作付内容 |
作付面積3.8ha(18年度)、収量400kg/a |
|
⑤購入価格 |
1kg当たり30円で組合より購入(品質評価し、±数円の価格差を設定) |
|
⑥作付品種 |
こしいぶき(早稲)、こしひかり、とどろき早稲(以上、食用)が中心。一部、北陸187号(専用品種)も使用。 これらの品種が選択される理由は、種の入手がしやすいうえ、食用種であれば育苗を分ける必要がなく、作業効率が良いことからである。 |
|
⑦給与対象牛 (中村牧場) |
乾乳期と泌乳後期に給与 |
3)飼料給与
・以前はTMRミキサーを所有し、自らTMR調製を行い給与していたが、
平成3年のミルキングパーラー・フリーストール体系導入と同時に配置の関係、
労働過多の回避等のために購入TMRを選択した。
・ここ2年半は10日に1回の配車(10t車)。
・調製については、飼料会社が代謝プロファイルテストの結果と検定結果の
乳成分をみながら実施。
・泌乳後期の牛については、BCS調整のために分離給餌を実施
・育成期におけるルーサン乾草主体の給与で発育良好(初産24ヵ月)
4)受精卵移植の取り組みについて
(1)中越受精卵移植研究会の活動
|
①構成・設立 |
・平成12年に酪農家15人で立ち上げ ・15人の概要は、年齢構成30~50代、主な経産牛飼養規模20~30頭 |
|
②採卵牛 |
・ホルスタインの改良を目的として開始したが、現在は肉用子牛の生産にも重点を置いている ・現在研究会で肉用牛2頭、ホルスタイン1頭を採卵牛として所有 ・肉用2頭→市営牧場に預託、ホルスタイン1頭(長岡市内の酪農家に預託) ・平成18年は肉用2頭で合計10個の受精卵を採卵するとともに、県から4個の受精卵の提供を受ける ・採卵の目標は約20個 |
|
③移植方法・料金 |
・県の家畜保健衛生所に頼んで実施 ・技術料(手術費+ホルモン剤投与)3万円/回+凍結費 |
|
④受胎率 |
1/3 |
|
⑤しくみ |
|
|
|
|
(2)中村経営のETの取り組み状況
・経営主自ら受精卵移植師の資格をもつ
・17年は2頭を移植(1頭を家保の獣医に頼む、1頭を自力で実施)
・ET産子牛は県内の家畜市場(上越、年4回開催)に出荷するほか、一部前橋にも出荷
5.環境保全対策~家畜排せつ物の処理・利用方法~
(1)処理方法
①ホイルローダーを利用して、牛舎より一段低くなったたい肥舎へふん尿を排出
![]()
②モミガラを混合して水分調整
![]()
③発酵舎において通風発酵および切り返し(タイヤショベル利用)
(2)利用方法
平成17年に自走式マニュアスプレッタを購入し、以下の方法で散布している。
①飼料畑へ散布
②共同散布
・隣の集落で特別栽培米を作付けしている個人と集団転作組合の計14haに散布を実施(散布量1t/a)
・散布については、生産組合と中村さんが共同作業で実施している
・散布料金4,500円/10aを徴収し、機械、原料、作業費にあてている
・課題としては、散布能力に応じたたい肥の運搬ができていないこと(ダンプが1台のみ)、
及び散布時期が限られることである。
6.生産部門以外の取り組み・地域活動
・「地域の農業を考える会」に参加し、小学生の農業視察研修先として協力している。
・地元の農業高校では乳牛の飼養を中止したため、酪農研修が出来なくなっている。
このことから農業高校生による2泊3日の研修を受け入れ、実習場所の提供を行っている。
Ⅲ 今後の課題
・規模拡大は考えていない。乳量水準は9,000kg/頭程度の維持を考えている。
・夫婦2人の労働力につき、育成を減らし、産次を延ばすことでコスト低減、労働の軽減を考えている。
・ETによる和子牛生産ついては、今後、付加価値生産のために重要であるが、2頭の採卵牛から
より効率的な採卵ができるよう、目標の20個採卵を目指していきたいと考えている。
Ⅳ 写真
|
成牛舎 |
ミルキングパーラー(平成3年導入) |
|
ET和子牛 |
データを徹底的に活用している |
|
転作田を利用した飼料畑(奥へと続いている) |
たい肥舎 |
|
ミレット |
ロールベール・ラップサイレージ体系を導入 |