茨城県・大子町受精卵移植研究会
学校法人福原学園 常務理事 堀尾房造
1.取り組みの概要![]()
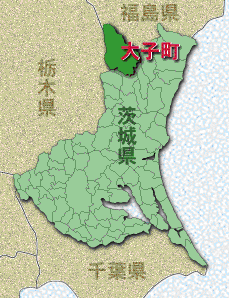 |
大子町受精卵移植研究会は、酪農家が地元の農業科高校生や指導支援機関との連携によって受精卵移植を中心とした活動を行い、地域酪農の所得向上、県内有数の肥育もと牛供給地域の維持等に貢献してきた事例であり、平成15年度畜産大賞地域振興部門に出品された事例である。 |
(1)研究会設立の背景
当研究会は平成2年に発足した酪農家グループであり、設立の背景要因として次の3点が指摘できる。
第1は、地域が進めた大子一高の農業科存続のための運動「地域農業活性化プロジェクト」の存在である。茨城県立大子一高の農業科が農業高校再編整備の検討対象になり、募集停止の噂に危機感を持った大子一高の卒業生グループ「若葉会」が大子一高農業科と一体となって「地域農業活性化プロジェクト」を推進した。同プロジェクトは6部門から構成され、このうち大家畜部門のプロジェクトの目玉として大子一高農業科に受精卵採卵処理施設が設置され(平成2年6月)、この施設を使っての「受精卵移植」の教育内容が新設された。この大子一高の施設を核とした受精卵移植の取り組みが地域の畜産農家の関心を集め、組織的活動に発展していった。
第2は、町内の中核的酪農家においてET和子牛生産と肥育による乳肉複合経営への転換が検討されていたことである。大子町は茨城県北部の中山間地帯に位置し、畜産(肉用牛繁殖、酪農)、しいたけ、茶、りんご、米等の複合経営が多い地域である。とくに酪農経営では昭和54年の生乳生産調整、平成3年の牛肉輸入自由化の影響を受けて、乳代収入、スモールや廃用牛等の副産物収入の減少による収入が頭打ちとなっており、受精卵移植による和牛産子生産の期待が一層高まっていた。
第3は、県内有数の肉用もと牛産地の活性化策としての期待がかかったことである。町内では高齢化に伴って和牛繁殖農家の戸数が減少し、大子町畜産農業協同組合が開設する大子家畜市場への上場頭数が減少していた。繁殖農家において繁殖雌牛の資質向上のためにET技術の導入が期待されたほか、大子家畜市場の活性化のためにET和牛産子の上場に期待がかかっていた。
このように、[1]大子一高の農業科存続のための運動、[2]地元酪農家で構成する保内郷酪農組合を中心とするETによる収入拡大、[3]地元の大子家畜市場の活性化と繁殖雌牛の資質向上による収入拡大をねらって、県立大子一高、保内郷酪農組合、大子町畜産農業協同組合、県農業改良普及センターが参加して大子町受精卵移植研究会が結成された。いわば産学連携によって始まった地域振興活動である。
(2)活動に当たっての協力体制
採卵、授精にあたっては、県の畜産試験場の技術協力を得ながら現場実証を繰り返してきた。
受精卵移植にあたっては、以前に保内郷酪農組合の獣医師であった永瀬氏(現在は開業獣医師)が全面協力する形で今日に至っており、最近は永瀬氏が研究会事務局も兼ねている。
2.研究会の活動実績と成果![]() (3
(3
これまでの活動実績と成果について、冒頭に挙げた研究会発足の契機となった3点に沿って分析すると以下のとおりである。
第1の大子一高農業科の存続に関しては、15年後の現在まで存続し、受精卵移植のための施設整備とドナー牛の導入によって農場実習の一環として農業教育に貢献している。なお、平成18年4月からは県立大子一高と県立大子二高(女子高)が統合して大子清流高校となるが、農業科は総合学科自然科学系列として引き継がれることになった。
第2のETによる酪農振興に関しては、平成14年当時40戸で1,000頭を飼養していた町内の酪農家は平成18年春現在38戸で1,200頭を飼養しており、戸数減少に歯止めがかかっている。ET利用農家は年次間で変動があり、平成14年の25戸に対して17年は15戸と減少しているものの、利用農家はET和牛産子による収入の増大効果を高く評価している。
第3の大子家畜市場の活性化に関しては、平成3年当時の1,748頭から毎年40〜50頭ずつ減少し、平成17年は958頭になっているが、下げ止まり感が見えてきている。研究会発足当初は酪農家中心のETであったが、平成17年には5戸の繁殖農家でもETを行うようになっている。
3.活動の継続を支えてきた背景![]() (4
(4
発足後15年を経過した現在も研究会活動が地域の畜産振興を下支えしている要因としては、次の諸点が考えられる。
第1は、先述したように研究会が個人会員制ではなく、高校、酪農協、畜産組合等の組織を母体に構成されていることである。生産農家はこれら組織の構成員であれば受精卵移植を受けられることができる。つまり受精卵移植を受けた農家がその年の研究会の生産農家となり、個人会員制のように年会費は徴収していない。このようなある意味でルーズな受益者負担の形式が、長続きした一因でもある。
なお、現在の受精卵移植の経費は、種代(受精卵)4万円+移植技術料1万円の計5万円であり、希望農家は移植1週間前までに研究会事務局の永瀬獣医師に申し込むことになっている。一方、ドナー牛の借り上げ料(1腹5万円)は、研究会が所有者に対して支払いを行う。
第2は、受精卵移植の着床率が高いことである。このことは永瀬氏の技術力によるところが大きい。近年の平均着床率は50%強で推移しているが、平成5年には着床率74.6%を達成し、北海道を抜いて第1位となった実績も持っている。なお、着床率は生づけが高く、凍結卵は下がることから生づけ優先の対応がとられている。
第3は、先述したように受精卵移植経費が5万円に抑えられていることである。県の畜産センターが事業等を活用して採卵・授精を無料で実施しており、このことが低コストの実現につながっている。
なお、ドナー牛は平成13年頃までは大子一高で導入・提供してきたが、現在は生産農家6戸もドナー牛を保有し、町内に乳牛8頭、和牛6頭が飼養されている。
第4は、県内の他地域との連携である。家畜市場上場頭数の減少は下げ止まったが、より積極的に上場頭数を増やすため、県内酪農家との連携体制を構築している。具体的には、県内の美野里酪農協管内の搾乳中心の大規模経営(A牧場)と協定し、牧場の乳牛を借り腹にET和子牛を生産し、生後2ヵ月(通常の市場上場月齢は8ヵ月前後)で大子町畜産農家が買い取り、肥育ないしは繁殖用に仕向けるという連携の仕組みを構築した(買い取り価格は市場平均価格の半値ほど)。この協定に基づき、平成18年1月、3月の開催にそれぞれ3頭が上場されている。
また一方で、他地域との連携による活動は、受精卵移植を大子町だけで実施すると受精卵が余ってしまい、凍結保存せざるを得なくなり、ひいては着床率の低下に繋がるといったことが起きるという、活動の悪循環の対策としてもニーズがあり、推進されてきた。
上述のように、大子町受精卵移植研究会は発足後15年を経過し、町内畜産農家のET利用農家数に年次変動はあるものの、町の畜産振興に大きく貢献していると言える。ET利用農家の研究会活動に対する評価は高く、他の地域への普及の可能性は高いと言える。
4.今後の課題![]()
当研究会の活動は定着し、町の畜産振興に寄与しているが、今後の課題としては次の諸点が指摘できる。
第1は、研究会の受精卵移植の対象が町内の酪農家と和牛繁殖農家であり、受精卵移植希望農家の数が少ない点である。さらにドナー牛の増加によって受精卵が余り気味であり、凍結保存が増えて着床率が下がっていくという悪循環を起こしている。この問題を打破するために、研究会組織をより一層広域化し、受精卵採取数と移植のバランスを取り、生付けによる着床率の上昇を図ることが課題となっている。
第2は、受精卵移植農家の中心が酪農家であり、酪農家戸数の減少もあって、黒毛和牛のET産子の数の増加に限界がある点である。ETの借り腹となる乳牛の増頭対策が必要となるが、町内では飼料生産基盤等の制約がある。この解決策の1つとして、先述したように町外のA牧場との協定を行うなどの取り組みを開始している。今後はこの問題点を解決する意味からも当研究会活動について隣接町村を含めた広域化することが必要になってこよう。
第3は、大子家畜市場の存続である。当市場は大子町畜産協同組合が開設者であり、上場するのは町内の畜産農家がほとんどである。そのため、町内の家畜飼養頭数の減少が上場頭数の減少に直結するという小規模市場ならではの運営の難しさがある。しかしながら、年6回の市場開設日は町内の畜産仲間が交流する場でもあるため、組合員から継続を希望する声が多く出ているのも事実であり、厳しい運営面とは別の意味で地域畜産の維持に貢献しており、難しい課題である。
5.写真等![]()
 採卵の様子 |
 |
 受精卵移植によって生まれた子牛 |
 借り腹の牛 |
6.関連情報![]()
・「夢を求めて」〜地域畜産業の活性化に大いに貢献した受精卵移植技術〜(いばらきの畜産情報:茨城県畜産協会)
![]()