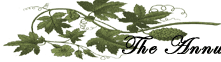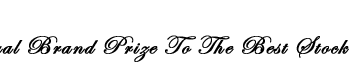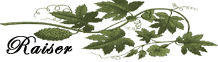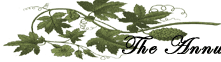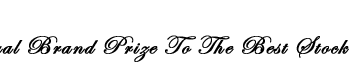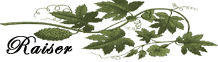|
平成21年度畜産大賞中央全体審査委員会と経営、地域振興、研究開発の各部門の審査委員会を代表して、審査の結果と「畜産大賞」選考の経緯について報告する。
今年度審査の対象となった出品事例は、経営部門11事例、地域畜産振興部門23事例、研究開発部門23事例で、合わせると「畜産大賞」の選考対象は57事例となった。
審査の結果は別掲の通り、「畜産大賞」は地域畜産振興部門で最優秀賞を受賞した、鳥取県畜産農業協同組合であり、出品タイトルは「『農業・畜産の“センチュリープラン(百年計画)”』~持続できる農畜産業を目指して~」である。
最優秀賞は経営部門が宮崎県児湯郡川南町の山道義孝氏による高収益安定養豚経営であり、出品タイトルは『「肉豚の高品質化と繁殖成績の向上が発展の条件と考える一貫経営」~6次産業への挑戦~』、研究開発部門は宮崎県宮崎市の肉質光学評価グループによる、光学手法に着目した脂質特性の基礎的研究、光学装置の試作・改良、そして現場での実証試験を産官学メンバーで取り組んだもので、出品タイトルは「光学的手法による食肉脂質評価装置の開発」である。
これらの受賞事例の具体的な内容については、受賞者の業績が本号に掲載されるので、本稿ではそれぞれの受賞事例の概要と評価の根拠となった特徴点を中心に紹介したい。
まず、「畜産大賞」を受賞した鳥取県畜産農業協同組合についてである。この組合は前身となる1980年設立の東部畜産農業協同組合から数えて、本年で30周年を迎える。畜産農業協同組合という名称だが、もともと、この組合は酪農家を中心とした組合である。組合員である酪農家は、生乳を大山(だいせん)乳業協同組合に出荷し、乳代金を稼いでいる。
一方、酪農経営で生産される乳用牛雄の肥育、牛肉の生産・販売部門は同協同組合を活用する仕組みを作った。つまり、乳と肉の協同組合組織を上手に機能分担させ、所得の向上、地域の活性化を図ってきたことが大きな特徴である。初めの20年間を第1期とすれば、その時期には主として組合員酪農家の副産物であるヌレ子(初生子牛)の哺育・育成・肥育・加工に取り組んできた。この乳用種肥育牛は当初から京都生活協同組合との産直事業で販売され、ヌレ子の付加価値形成へとつながった。
その過程で、生協組合員が生産の現場に強い関心を寄せはじめた。生協側は常に安全な、素性の分かる牛肉を求め、どのようなところで牛が飼われているのかを見たいと言い始めた。都会の消費者の多くは牧歌的な放牧風景をイメージしているようだった。しかし、鳥取県東部は大山裾野とは違い、舎飼い中心だった。そこで都会の人を失望させないような牧場をつくろうと畜産農協組合員は総事(そうごと)を行い、手づくりで緑豊かな山の中に、COOP美歎(みたに)牧場を建設した。そこは「もの」の交流だけでなく、「ひと」の交流も大切だと考える生協組合員と畜産農協組合員の格好な交流拠点となり今に到っている。
一方、生産者も京都生協に大勢出かけて、牛肉などの販売促進、試食会開催などを行って相互理解を深めている。牛舎をはじめ牧場のバーベキューハウスなどは建設コストを低減させるため廃材を活用し、また不用となったさまざまな資材を入手し完成させたが、今でもそれを利用し続けている。
次いで、哺乳センター、さらに衛生面で最先端をいく食肉処理加工場、地域から絶大なる支持を得ている直売所、集客力抜群の試食体験施設を含む「フレッシュパーク若葉台」を県の要請を受けて工業団地の一角に設立した。このようにして食肉の生産から処理、加工・販売までの一貫したフードチェーンをつくりあげた。その過程で、はじめはもっぱら京都生協向けのCOOP鳥取牛ブランドの確立を意識したが、やがて徐々に直売所を介した営業拡大によって地元消費者との交流を深め、地域に信頼関係を強くしていった。
続く第2期は2001年以降で、組合員の多くは第2世代となり、更なる発展に向けて、センチュリープランの理念を掲げ、再生産可能な畜産・農業のあるべき姿を、①環境の積極的保全、②農業後継者の確保、③有限な資源の循環、④健康への食を通した積極的なかかわり方、⑤都市と農村の共生、⑥食料の自給を目指し、今日的政策課題となった安全な畜産物の6次産業化による畜産物供給体制を、理念だけでなく経済的にも合理的に確立しようとした。さらに地域資源循環型畜産を確立し、地元消費者に信頼され、地域に根ざした畜産を構築しようとした。
そのため遊休水田を中心に稲発酵粗飼料の積極的な生産に取り組み、やがてたい肥を水田に還元する耕畜連携システムの構築のために、この畜産農協組合が出資した(株)東部コントラクターがコーディネータ役を担うこととなった。さらに、この会社は全国的にみても類がない地域の水田農業協議会に参加して、水田生産調整の担い手と位置づけられている。また、同じように出資した㈲TMR鳥取は廃材などを利用した手づくりの工場で、地域で生産される稲発酵粗飼料と生協商品等の製造過程で発生する食品副産物のエコフィードを利用して、年間を通して、一定の品質の資源循環型TMRを酪農家、肥育農家、直営牧場に供給して、主として地場消費向けの新しい牛肉ブランドを立ち上げた。また、2005年には牛肉の生産現場から食卓までを基本に食品安全のマネージメントシステムISO22000を取得し、生産物の安全を担保するシステムを確立した。
以上のように鳥取県畜産農業協同組合は壮大な理念を堅実に実践へと結びつけ、畜産物の安全なフードチェーンを構築することで、食と農の再生に向けた新たな地平に到達しつつある。1995年ころには京都生協を中心とする生協への出荷が食肉生産量の50%であったものが今ではそれが25%となり、地場消費が著しく増え、地域貢献度が高まったことが分かる。背後に巨大な消費地を持たないこの地域で、畜産専門農協がこのような業務展開ができたことは地域畜産振興に向けた普及性に多大な示唆を与え、今後の発展性が十分見込まれる点が「畜産大賞」に値するものと評価された。
続いて、その他の最優秀賞受賞事例についてである。経営部門の山道義孝氏は母豚370頭規模の養豚経営で、飼養環境の改善を心掛け、豚のストレスを軽減し、衛生管理プログラムの導入などで高い繁殖技術を基礎とした高品質肉豚を生産している。肉豚としては地域7農場と連携して高付加価値化を図って「あじ豚」ブランドを確立した。そして精肉のほかハム・ソーセージの加工販売・レストラン経営に乗り出して、経営の6次産業化に成功した。このブランド化は生産グループ内で種豚、交雑方式、飼料の統一化を行うことで実現している。また、高い繁殖成績による高生産性、販売先との定額販売契約、飼料の一括購入による購買条件の改善などによるコストの引下げで、高い収益性をあげている。
長男、次男、三男に別々の専門教育を受けさせ、それを生かせる仕事を経営内につくり、後継者として立派に育成し、家族全員による経営の立体化に成功している。また地域の産業廃棄物であった焼酎(しょうちゅう)廃液を研究機関と連携して発酵飼料として実用化した。さらに地域の学生生徒の研修や体験学習を通して養豚への理解促進にも腐心してきた。
2003年、宮崎県養豚生産者協議会の設立に努め、会長として組織をまとめた。その後2006年には日本養豚生産者協議会の設立に関与し、養豚農家の組織化による情報の共有化、意識の向上、関係団体との協調などにより、養豚業の振興に大きく寄与した。
このように同氏は輸入豚肉の増加や消費の低迷などによって苦境に立つ養豚経営が生き残りをかける上での先駆的モデルを作り上げた。
次に、研究開発部門の肉質光学評価グループについて述べる。産官学でグループを構成し、8年間にわたる共同研究によって、食肉ラインで脂質を迅速かつ安全に評価できる小型で、しかも安価な光学装置の開発を試みた。
一般に肉質の中で脂質は格付け、保存性、健康、食味にかかわる重要な要因と認識されているものの、従来、外観や触感によって評価されてきた。その際、温と体など異なった肉温での脂質の比較は食肉検査員でも困難であり、より科学的、客観的な評価基準の策定が求められていた。そこで工学分野で進展の著しい光学手法に着目し、食肉脂質評価装置を開発することにした。
まず、牛、豚について、流通している脂質の実態を把握し、和牛やLWD交雑豚などにおいて、その理化学的性状に幅広い分布があることを見出した。次いで理化学的測定値相互の関連性などを明らかにし、脂質にかかわる物性や光学特性の基礎的知見を得た。
この基礎的知見を生かすため、当時、肉色評価やPSE豚肉の評価に用いられ始めていた最先端の可視光、光ファイバ法を、初めて牛と豚の脂質に応用し、脂質の融点、屈折率、硬度、飽和脂肪酸量を評価する装置の試作と改良に努めた。その結果、挿入型プローブから完全非破壊となる接触式プローブへと変遷しながら、安価で迅速な測定が可能で、しかも携帯できる小型の光ファイバ装置の開発に成功した。
開発した装置による迅速な評価値は肉質の一つの経済的指標として役立つだけでなく、消費者へつながる新たな情報としての価値を有している。そして、これを生産へフィードバックすることにより、新たな育種指標や栄養管理の指標としても役立つとの期待がもたれている。
以上、「大賞」と2つの部門の最優秀賞の受賞事例について、その概要と評価の根拠を説明した。いずれの事例もそれぞれの部門において素晴らしい業績をあげ、大きな意義を持つ事例である。
「大賞」は異質な部門の最優秀賞の中から選ぶことになっている。そこに審査の難しさがあるわけだが、日本畜産の置かれている現状と将来方向に照らして、総合的な判断に基づいて、今、表彰する意味合いを考えて選んだ。
時間の関係で講評を割愛せざるを得ないが、最優秀賞に至らなかった各部門の優秀賞および特別賞受賞事例、残念ながら選外となった事例についても、それぞれの部門において、優れた実績を持つ事例ばかりであった。それらの事例をも含めて、その内容が日本全国に広まることによって、この表彰事業が日本畜産の前進にいささかなりとも寄与することができることを願っている。
(みやざき あきら・学校法人二本松学院学院長 京都大学名誉教授)
|