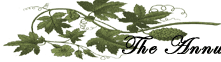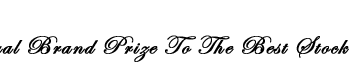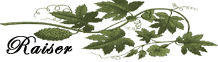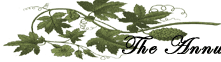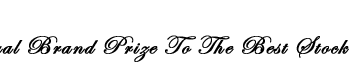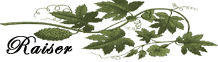|
中央全体審査委員会と各部門の中央審査委員会を代表して、審査の結果と「畜産大賞」選考の経緯について報告します。
今年度審査の対象となった出品事例は、経営部門9事例、地域畜産振興部門13事例、研究開発部門14事例で、合わせますと「畜産大賞」の選考対象は36事例になります。
審査の結果は別掲の通り、「畜産大賞」は研究開発部門で最優秀賞を受賞しました、北海道大学大学院獣医学研究科 動物疾病制御学講座 微生物学教室であり、出品タイトルは「インフルエンザウイルスの生態解明とライブラリーの構築――高病原性鳥インフルエンザの診断と予防への応用―」であります。
最優秀賞は経営部門が沖縄県石垣市の多宇司(たうつかさ)・多宇(たう)明子(あきこ)氏による自給飼料を活用した肉用牛繁殖経営であり、出品タイトルは「暖地型牧草を活用した輪換放牧と採草利用による肉用牛繁殖経営――60歳定年、後継者へバトンタッチ―」、地域畜産振興部門は山形県遊佐(ゆざ)町(まち)の飼料用米プロジェクト(飼料用米生産による自給率向上に関する調査検討プロジェクト)による飼料用米を活用した養豚を中心とする農工消連携であり、出品タイトルは『「こめ育ち豚」で広げる水田農業と消費の輪―食べる手・作る手・つないで食の再興計画 遊佐(ゆざ)モデルのチャレンジ』であります。
これらの受賞事例の具体的な内容につきましては、この後、行われます業績発表において受賞された方々から詳細報告されることになっておりますので、私からはそれぞれの受賞事例の概要と評価の根拠となった特徴点を中心に紹介したいと思います。
まず、「畜産大賞」を受賞しました北海道大学大学院獣医学研究科 動物疾病制御学講座 微生物学教室についてであります。
高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するとともに、発生時における蔓延防止を図ることは、畜産物の安定供給とヒトへの感染防止のために必須の課題であります。
この教室は、国際獣疫事務局(OIE)のレファレンスラボラトリーなどの役割を担い、鳥インフルエンザの診断、サーベイランス、技術指導などを実施し、高い実績を挙げています。また、ヒトの新型インフルエンザ出現に備え、ワクチン候補株の収集を進めるとともに、世界保健機構(WHO)、厚生労働省などの行政機関との緊密な連携も高く評価されています。
評価される点の1つ目は、アラスカとシベリアにおけるそれぞれ3年間に及ぶ現地調査研究を基に、家禽、家畜およびヒトのインフルエンザウイルス遺伝子の起源はすべて野生水禽のウイルスにあることをつきとめたことです。つぎにインフルエンザウイルスライブラリーを構築し、診断や予防法を開発に利用しました。これらの研究成果は国際的に評価の高い海外学術雑誌に121報発表されているほか、著書、学会発表、新聞発表として公表されております。
評価される点の2つ目は、確立したインフルエンザウイルスライブラリーを利用して、H5およびH7亜型特異的簡易診断キットをメーカーと共同開発したことです。この診断キットを用いることにより、従来法より簡便かつ迅速にウイルス抗原の検出とHA亜型の同定を行うことが可能となりました。
また、ウイルスライブラリーの中から高病原性鳥インフルエンザワクチン製造株として有用なウイルス株を選抜し、国内メーカー4社とH5N1およびH7N7ウイルスワクチンを共同開発されました。
評価される点の3つ目はOIEの高病原性鳥インフルエンザレファレンスラボラトリーに指定されていることに鑑み、アジア各国の高病原性鳥インフルエンザが疑われる検体を受け入れ、診断していることです。これまでにモンゴル、ラオスなどから受け入れた検体について、迅速に診断し、当該国とOIEに報告しました。また、この教室はこれまでに2004、2006、2007および2008年に鳥インフルエンザの診断トレーニングコースを提供してまいりました。本コースはアジア各国の鳥インフルエンザの診断技術向上を目指したもので、発生・流行に即応するための技術面での指導を行っております。これらのトレーニングコースを通して鳥インフルエンザの診断に携わる技術者を養成し、各国の防疫対策に多大な貢献をしております。
以上のように、この教室はOIE、FAOおよびWHOのそれぞれ、レファレンスラボラトリー、サーベイランス拠点およびヒトと動物間インフルエンザネットワークの拠点として、高病原性鳥インフルエンザ制圧に向けた取り組みを継続し、高病原性鳥インフルエンザの世界的な研究拠点として見るべき成果を収めていることが「畜産大賞」に値するものと評価されました。
続いて、その他の部門の最優秀賞受賞事例についてであります。経営部門の多宇司(たうつかさ)・多宇(たう)明子(あきこ)氏は亜熱帯海洋性気候による温暖湿潤で、年中草が生育する立地条件を生かした肉用牛繁殖専業経営を行っておられます。平成11年に家族全員で家族協定を締結されましたが、経営は夫婦のみで実質的に担われ、多宇司(たうつかさ)氏は繁殖牛の飼養管理、草地管理を、多宇(たう)明子(あきこ)氏は子牛の哺育・育成、経理関係を分担しておられます。
平成12年、繁殖牛を100頭規模に拡大したのを機に、ジャイアントスターグラスで利用する放牧地18haを電牧を用いて16牧区に細分して集約的周年輪換放牧を行ってきました。その後も増頭を続け、現在、繁殖牛を142頭飼養しておられます。肥培管理に意を尽くしてきたので草地の生産性は高く、収量は年間120t/haにもおよび、高い粗飼料自給率(92.9%)を実現しておられます。
子牛分娩は初妊牛を除いて、すべて放牧地での自然分娩として省力化に努め、生後10日目程度で早期母子分離とし、子牛を哺乳ロボットでの管理に移すため母牛はほぼ1年1産を続けています。放牧中の事故もほとんどみられません。周年放牧と哺乳ロボットの導入によって、省力化が実現されており、ゆとりある経営になっております。
以上のような緻密な飼養管理によって、高価格の子牛を低コストで生産しているため、家族労働力1人当たりの年間所得は1,300万円弱に達しています。現在、飼料用穀物価格が高騰しており、輸入穀物にもっぱら依存している畜産経営は危機的状況に追い込まれつつある中で、この経営のような高い飼料自給率で経営を安定させている事例は、わが国の繁殖牛経営技術の改善に大いに参考とすべきものであり、とくに離島地域畜産振興にあたっては模範的事例として高く評価できます。
次に、地域畜産振興部門の飼料用(しりょうよう)米(まい)プロジェクトについてであります。このプロジェクトでは飼料用米生産者、豚飼養者、農協、飼料会社、食肉加工業者、消費者・団体などが連携してクラスターを形成し、わが国の畜産が抱える構造的問題点を地域的な取り組みによって少しでも解決しようとしている好事例であります。
山形県遊佐(ゆざ)町(まち)で、平成16年に21名、7.8haから開始された飼料用米の作付けは、平成20年には286名、168haに拡大し、転作田の活用と耕作放棄地の回避に結びついています。加えて、飼料用米の生産利用は食料自給率の向上と地域資源である水田の利活用につながり、わが国の畜産を少しでも強固なものにしようという先駆的な取り組みであり、他が学ぶべき地域畜産モデルとしても高く評価できます。
このような動きが拡がれば、世界的にみて極端に長いわが国のフィードマイレージが短縮されることと期待されます。
現在、飼料用米は豚の肥育後期(80日)にとうもろこしの10%相当量が給与され、豚肉の品質面で好成績を収めるとともに、豚のふん尿が飼料用(しりょうよう)米(まい)の栽培にも利用されることで循環型農業の構築に役立っています。
転作田では栽培された飼料用米は玄米1kg当たり46円で販売され、産地づくり交付金と合わせて10a当たり約6.6万円の農家収入になっており、当該地域の農家所得の形成に役立っています。さらに飼料用(しりょうよう)米(まい)の食用への転用の防止についても十分な配慮がみられている点も評価されます。
以上のようにこのプロジェクトはいわゆる農工消連携を通して、「情報を共有化できる取り引き」を実現し、安全・安心なフードシステムを構築しており、今後の日本畜産の進路に多大な示唆を与えるものと判断されました。
以上、「大賞」と2つの部門の最優秀賞の受賞事例につきましては、その概要と評価の根拠を説明させて頂きました。いずれの事例もそれぞれの部門におきまして素晴らしい業績をあげ、大きな意義を持つ事例であります。
「大賞」は異質な部門の最優秀賞の中から選ぶことになっております。そこに審査の難しさがあるわけでありますが、日本畜産の置かれている現状と将来方向に照らして、総合的な判断に基づいて、今、表彰する意味合いを考えて選ばせて頂きました。
時間の関係で講評を割愛せざるを得ませんが、最優秀賞に至らなかった各部門の優秀賞および特別賞受賞事例、残念ながら選外となりました事例につきましても、それぞれの部門におきまして優れた実績を持つ事例ばかりでありました。それらの事例をも含めまして、その内容が日本全国に広まることによって、この表彰事業が日本畜産の前進にいささかでも寄与することができればと願っております。
最後になりましたが、受賞されました皆様方に心からお祝いを申し上げるとともに、今後の一層のご活躍を期待して、審査講評を終わらせいただきます。ありがとうございました。
|