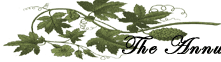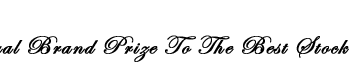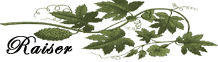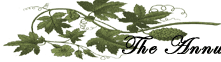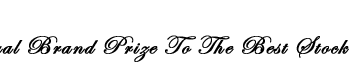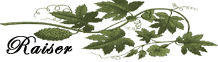|
中央全体審査委員会と各部門の中央審査委員会を代表して、審査の結果と「畜産大賞」選考の経緯について報告します。
今年度審査の対象となった出品事例は、経営部門12事例、地域畜産振興部門16事例、研究開発部門11事例で、合わせますと「畜産大賞」の選考対象は39事例になります。
審査の結果は、別掲の通り、畜産大賞は経営部門で最優秀賞を受賞しました北海道の小葉隆さん・小栗美笑子さん夫妻の経営する酪農経営であり、出品タイトルは「人・牛・大地の融合――ロマン美らせた放牧礁農」であります。
最優秀賞は地域畜産振興部門が宮崎県の高千穂地区農業協同組合畜産部による繁殖牛を主とした肉用年増頭への取り組みであり、出品タイトルは「山間地域における肉用年増頭の取り組み――山間地という悪条件を克服し、地域ぐるみの力で生んだ『6500頭』」、研究開発部門は株式会社機能性ペプチド研究所による受精卵移植技術に関連する研究開発であり、出品タイトルは「家畜体外授精卵生産用無血清培地の開発と製品化」であります。
これらの受賞事例の具体的な内容につきましては、この後行われます業績発表において受賞された方々から詳細報告されることになっていますので、私からはそれぞれの受賞事例の概要と評価の根拠となった特徴点を中心に紹介をしたいと思います。
まず、畜産大賞を受賞しました小栗隆さん・小栗美笑子さん夫妻の経営する酪農経営についてであります.
この経営は北海道の西南部、函報から車で2時間ばかり北上したところに位置する八雲町にありまして、50.5haの草地を基盤に経産牛年間平均45頭を飼養する経営です。平成9年に、濃厚飼料依存・乳量追求といった従来型の酪農から放牧酪農に転換し、夏の間は昼夜放牧、冬は昼間だけパドックに放し飼いする独自の技術体系を築き上げ、低コスト・高収益経営を確立して現在に至っております。
評価される点の1つ目は、大牧区をベースにした草地利用技術、放牧管埋技術であります。通常、考えられる輪換放牧に対して、夜間放牧用と昼間放牧用の2つの大牧区を設けて、その中に草の生育状況に合わせて一時的に採草利用地を囲い、面積を広げたり狭めたりしながら採草対象地を移動させて、常に放牧利用地の草丈を20㎝程度にそろえています。
草の生育状況に合わせて放牧地を移動させるいわゆる輪換放牧とは対昭的な大牧区での固定放牧でありますが、放牧利用と採草利用を組み合わせることによって牧柵への投資を抑え、省力的で輪換放牧に勝るとも劣らない集約的な草地利用を実現しています。
評価される点の2つ目は、土壌改良剤以外は化学肥料をまったく使わない資源の循環利用を基本とした草地管理技術を確立していることです。
完熟たい肥と尿のみによる肥培管理で、適切な草生を維持し、採草専用草地では早生~晩生のオーチャードグラスとチモシーを組み合わせて収穫期間の幅を広げ、効率的な採草を可能にすることによって、化学肥料依存の他の経営と較べてもそれに劣らない収量を実現しています。
評価される点の3つ目は、補助飼料として給与する濃厚飼料も、非遺伝子組み換えで生産された収穫後農薬不使用のものに限定し、消費者の求める安全・安心なプレミアム牛乳を生産することによって高乳価を実現していることです。
評価される点の4つ目は、「牛にも人にも無理をかけない」「牛にできることは牛にやってもらう」ことを基本とした草地完全依存の飼養体系を確立することによって、大幅な濃厚飼料費の節減、肥料費の節減、雇用労働費の節減、さらに診療・医薬品費の節減を可能にし、驚異的ともいえるほどの生産コストの低減を実現していることです。
放牧酪農に転換する前と転換してからの比較数値の一例を申し上げると、経産牛1頭当たりの年間購入飼料費が17万6000円減少して3分の1以下に、化学肥料費がゼロになったことによって自給飼料の物財費が14万円ばかり減少して7分の1になったという具合です。
以上の総合された結果として、この経営の平成17年度の実績をみますと、
年間所得総額: 1370万6000円
経産牛1頭当たり年間所得: 30万5000円
家族労働力1人当たり年間所得:548万3000円
乳飼比::13.5%
生乳1kg当たり生産原価; 42.1円
粗飼料の自給率は100%で、濃厚飼料を含めたTDN換算飼料自給率は74.9%と抜群の成績を示しています。
今回、この事例が「畜産大賞」に値すると評価されたのは、酪農ひいては畜産をめぐる近年の厳しさを増す状況の下で、この事例が問題打開に対する一つの有力な方向を示しているとみられることにあります.。
周知の通り、化石燃料に代わるバイオエタノール生産の原料仕向けとの競合によって飼料穀物価格が高騰し、穀物飼料依存度の高い経営は危機的状況に追い込まれています。さらに、カロリーベースでとらえた日本の総合食料自給率は40%を下回り、これを引き上げることが食料確保の安全を保つ上での重要課題になっています。
食料自給率を引き下げている最大の要因は輸入飼料に依存する畜産にあるとされており、飼料自給率の引き上げは畜産の経営的な視点からみても、食料需給の観点からみても、政策上の最重要課題として位置づけられています。
小栗隆さん・美笑子さん夫妻によって築き上げられた酪農経営は、このような課題に応える経営モデルの一つであるとして畜産大賞に値すると評価されました。
続いて、その他の部門の最優秀賞受賞事例についてであります。
地域育産振興部門の高千穂地区農業協同組合畜産部は、平成6年に高千穂町、五ヶ瀬町、日之影町の3つの農業協同組合が合併して新たに発足した農業協同組合の畜産部であり、大分県と熊本県に境を接する宮崎県北部の辺境に位置する地域を活動範囲とする組織であります。
この辺りは九州山地の山々が連なる典型的な山間地域であり、経営規模が零細で過疎化が進み、ご多分に漏れず高齢化の進んでいる地域であります。
そのような地域で、この組織は、繁殖牛を主とした肉用牛の増頭に取り組み、平成10年から18年にかけての8年間に第1次目標、第2次目標を次々達成し、1000頭に及ぶ増預を実現して地域振興に大きく貢献しております。
活動の推進主体は、2つありまして、1つは肉用牛を飼っている農家全戸が加入している49の組織によって構成されている「農協畜産連結協議会」、もう1つは、県の出先機関、町、農協、共済等のすべての関係機関・関係組織に所属している技術職員が会員になっています「西臼杵郡畜産技術員協会」であります。
いずれも、農協畜産部が事務局を担当し、農協が立案した計画を「技術員協会」に諮って推進方策を具体化し、「連絡協議会」を通じて農家に伝え、「技術員協会」が計画達成に向けて指導支援する役割を担っています。
国・県の事業を活用して生産基盤を強化するほか、他県からの粗飼料の調達・供給体制を作り上げたり、「すけっと共生牧場」と名付けたヘルパー機能を持つサポートシステムを構築したり、「放牧ネットワークの会」を組織したり「高千穂アグリネット」といったコンピュータによる情報ネットワークを構築したり、さまざまな仕組みを工夫することによって、増頭を実現してきています。
農協を中核に、それぞれの組織独自の役割を踏まえながら、組織の枠を超えた技術員相互の一体的な連携による活動が、大きな成果をもたらす大本になっていると思われます。地域振興を目指す現地段階における企画・立案、指導支援の組織体刺のあり方と推進手法に学ぶべき多くの内容を持つ事例といえます。
次に、研究開発部門の株式会社機能性ペプチド研究所の研究開発についてであります。この研究所は平成2年に独立行政法人「生研機構」などの出資によって設立された研究開発会社でありまして、平成8年から自ら開発した家畜授精卵用培地の製造・販売を開始し、その後研究開発対象を拡大しながら現在に至っております。
今回審査の対象となったウシの体外受精卵生産用無血清培地の開発は、未熟卵を成熟させるための「卵子成熟用無血清培地」、体外受精効率を高めるための「媒精液」、受精卵の発生を促すための「無血清培地」の開発を内容とするものであり、従来の血清を用いた培地に比べて、ウイルスその他の感染の危険性がなく、ロット間の生産成績に変動のない、安全かつ安定的な体外受精卵の培養を可能にするものです。
実証試験の成績をみても、血清培地による場合に比べて受胎率が高くなり、死産率が低下し、子牛の生時体重のバラツキが少なくなるという結果を示しています。牛肉生産のためにと畜される優良系統牛の未熟卵を取り出して培養し、体外受精をして子牛を効率的に生産できるようにするならば、資源の有効活用に、また高品箕牛肉の生産増加に寄与することはいうまでもありません。
この研究所の研究開発は、体外受精卵の移植による肉用牛生産の進展に貢献するものとして、大きな意義を持つものといえます。
以上、大賞と2つの部門の最優秀賞の受賞事例につきまして、その概要と評価の根拠を説明させて頂きました。いずれの事例もそれぞれの部門におきまして素晴らしい業績を上げ、大きな意義を持つ事例であります。
毎年度申し上げることですが、「大賞」はまったく異質な部門の最優秀賞の中から選ぶことになります。そこに審査に当たっての大きな難しさがあるわけでありますが、日本畜産の置かれている現状と将来方向に照らして、大局的な観点から総合的な判断に基づいて、今表彰することの意味合いを考えて選ばせて頂きました。
時間の関係で講評を割愛せざるを得ませんが、最優秀賞に至らなかった各部門の優秀賞および特別賞受賞事例、残念ながら選外となりました事例につきましても、それぞれの部門におきまして優れた実績を持つ事例ばかりであります。それらの事例を含めまして、その内容が日本全国に広まることによって、いささかでもこの表彰事業が日本畜産の前進に寄与することができればと願っております。
最後になりましたが、受賞されました皆様方に心からお祝いを申し上げるとともに、今後一層の活躍を期待して、審査報告を終わらせて頂きます。
|