●平成10年度畜産大賞業績発表・表彰式
審査を振り返って
中央全体審査委員会委員長 荏開津典生
ご紹介いただきました荏開津でございます。中央全体審査委員会を代表して、第1回の畜産大賞の審査経過についてご報告申し上げます。
全体の審査は、4つの部門にわたり審査を重ね、最優秀賞その他を決定し、そのなかから、最後に中央全体審査会において畜産大賞1点を選びました。各部門ごとの詳細については、選考経過をご説明する時間がありませんので、最終的な大賞の審査についてだけご報告いたします。
最初に、今回が第1回ということなので、少しご説明をしておきます。この畜産大賞、経営部門、指導支援部門、地域振興部門、研究開発部門の4部門の最優秀賞各1点合計4点のなかから、大賞1点を選ぶというものです(表1)。
4部門は、それぞれ非常に違う領域のものであり、この大賞の審査は、必ずしも同じものさして比較できるものではありません。それぞれ違う部門から選ばれた最優秀賞であり、それぞれが立派な業績であります。
そのなかから、畜産振興という非常に大きな大局的な観点にたちまして、1点を畜産大賞に決定させていただきました。
本年度の各部門の最優秀賞に選ばれましたのは、経営部門では、栃木県那須の酪農経営:有限会社那須高原今牧場の今耕一さんの経営です。指導支援部門は、大分県久住町畜産センター:肉用牛を中心とした畜産の指導支援です。地域振興部門は、愛知県豊橋市の酪農協同組合:これは堆肥づくりを中心とした地域振興です。研究開発部門は、帯広畜産大学の品川森一教授のプリオン病の早期診断法の開発です。
以上のなかから中央全体審査委員会としましては、久住町畜産センターの活動に対して、本年度第1回の畜産大賞をさしあげたいということに決定いたしました。
この久住町が大賞にいたった審査経過について詳しくお話申し上げます。

荏開津審査委員長(千葉経済大学教授)
◎畜産大賞大分県:久住町畜産センター所長 左右田 保 |
〈指導支援部門〉
久住町の肉用牛生産は、ご承知のように広大な牧野を背景にした夏山冬里方式による、昔からの和牛繁殖地帯です。畜産センター設立に先だって、町では昭和54年に町内の肉用牛農家の自主的組織として、久住町和牛振興会が結成されました。
業績発表される久住町畜産センター所長の左右田さん
この組織を支援し、和牛を中心とした畜産の発展に貢献したいということで、昭和57年に町、農協および農業共済組合を基礎とする第3セクター方式で久住町畜産センターが結成されたわけです。
今日受賞したこのセンターの仕事の内容は、畜産の技術と経営の両面にわたり総合的な観点から指導を行い、また、さまざまな助言等が行われていることです。技術と経営とを一体的にとらえ指導・普及事業がなされているのがひとつの大きな特徴です。そしてまた、このセンターでは単に指導、助言だけでなくさまざまな実体的な活動も行われています。たとえば、畜産におけるヘルパーの活動とか、雌牛や子牛の取引きの仲介などの実体的な活動も行っておられます。
評価の大きなポイントをあげますと、まず第1にこのセンターは、単なる情報交換の場であるとか、協議会の場ではないということです。センターには専従の職員がつねにおられ、また、出向の職員も加わって実質的な指導・支援がきわめて継続的に行われています。

畜産大賞業績発表・表彰式に出席されたみなさん
第2には、旧来の粗放的な少頭数経営から市場性の高い集約的な大経営、これは日本の肉用牛がこれから進んでいかなくてはならない方向ですが、そういう方向への転換という、この地域の大きな課題に大きな貢献を果たしていることです。
その成果としては、同町の子牛の市場評価が近年非常に高まっているということと、雌牛の飼養頭数の増加にみられます。町の雌牛の目標頭数は3000頭で、いまや頭数はほぼそれに近いものになっています。頭数の増加にも成果が如実に現れていることが判断されます。
第3に、広大な牧野を生かした夏山冬里方式を発展させることによって、牧野の景観の保全、資源の保全に貢献し、これをとおして中山間農村の活性化にも大きな役割を果たしたことです。これは単に肉用牛部門のみならず、村全体の活性化にも大きな役割を果たしたこととして、評価する大きなポイントになりました。
以上を総括すると、指導・支援を通じ格段に優れた成果をあげられたことと同時に、牧野景観、資源の保全といった、現在のそしてこれからの日本の農業、とりわけ畜産業が大きな課題とする点について大きな貢献をされ、かつ中山間の農村の維持・発展、これも現代の日本の農村社会が直面している大きな課題としていることですが、これにも貢献されているということです。
このような大きな観点を総合的に評価いたしまして、第1回の畜産大賞に決定いたしました。
なお、同センターは、町長、農協組合長さん等の指導力がバックにあるのは当然のことですが、15年間の長きにわたり活動をリードしてこられました所長左右田保氏の貢献があったことも特筆に値するものだと考えます。
他の3点の最優秀賞につきましては申し訳ありませんが、簡単に話させていただきます。
◎最優秀賞栃木県:那須高原今牧場代表 今 耕一 |
〈経営部門〉
経営部門は、栃木県那須で酪農を営まれています高原今牧場:今耕一さんの経営する牧場です。経産牛115頭という、現在でも日本では最大級の酪農経営です。平均乳量は9000kg、乳脂率3.98%、細菌数3万以下のきわめて高い乳量と乳質、さらに黒毛和種ETを活用されるような先進的な技術も用いられ、高収益をあげられています。また、法人化によりさまざまな工夫をこらし、経営収益の追求と生活の豊かさの追求、この両面のバランスを求めておられるたいへん優れた経営です。
この経営は、本年度の農林水産祭におきまして畜産部門の天皇杯を受賞されています

業績発表される那須高原今牧場代表の今耕一さん
◎最優秀賞愛知県:豊橋市酪農農業協同組合代表理事組合長 河合正秋 |
〈地域振興部門〉
本組合の活動は、組合を中心とした堆肥の生産と供給です。畜産の廃棄物の問題はたいへん重要なもので、これからの日本の畜産業が解決していかなければならない大問題です。豊橋市では豊酪方式、分散方式の堆肥施設で、狭い集落の事情に適したいくつかの堆肥の施設を配置しまして、耕種農家の76%がこれを利用しているという、高い優れた成績をおさめておられます。
豊橋市はご存じのように混住化が進む地帯で、畜産廃棄物の問題はきわめて深刻ですが、このような地域にあってはモデル的な成果をあげられていることで、この部門で最優秀賞に選ばれたわけです。

業績発表される豊橋市酪農農業協同組合代表理事組合長の河合正秋さん
◎最優秀賞帯広畜産大学教授 品川 森一 |
〈研究開発部門〉
最後に、研究開発部門についてです。帯広畜産大学品川教授のプリオン病、いわゆるイギリスで発生し、非常に深刻な問題となりました狂牛病です。これは、初めはヒトにはうつらないといわれていましたが、後に人獣共通の伝染病であることがわかり深刻な問題となり、その対策は緊急な課題となっています。同教授は世界に先がけ、この病気の早期診断法を開発されました。ご研究ははやく、1991年の「ヴェテリナリ・レポート」に発表され、その後多くの世界の雑誌に取りあげられ、また国際獣疫事務局、家畜の病気についての国際的な権威ある機関においても、この早期診断法は取りあげられています。
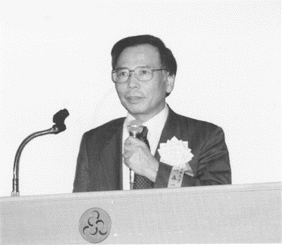
業績発表される帯広畜産大学教授の品川森一さん
きわめて優れた業績であることから、本年度の最優秀賞に選ばれました。
以上、時間の関係で3部門について簡単にしか述べられなく誠に恐縮ですが、後ほどそれぞれについて詳しいご発表がありますので、お聴きいただきたいと思います。
この大賞は、それぞれの優れたお仕事を顕彰すると同時に、これを広く普及いたしまして、日本全体の畜産の発展に貢献したいということでございます。これから発表されるなかからいろいろなことを学ばせていただき、今後の日本の畜産の発展に貢献することを祈念いたしまして、中央全体審査会の審査経過報告にかえさせていただきます。