「豊酪方式」分散型畜産環境整備の成功
渡邊 昭三
◎最優秀賞:地域振興部門愛知県豊橋市酪農農業協同組合 |
1.地区の紹介
豊橋市は、愛知県の東南に位置し、東は静岡県に境を接し南は太平洋に臨み、人口は35万人余を有し、名古屋に次ぐ県内第2位の都市として発展してきた。気象は、南方を太平洋の暖流が流れ、北には山地があって比較的温暖で、農業に適している。また、名古屋をはじめとする東西の消費市場に近いという経済的条件にも恵まれた立地を背景に、過去20数年来全国1位の農業粗生産額である。農業の経営類型についても、施設園芸・畜産を中心とする施設(資本集約型)農業だけでなく、稲作・露地野菜・果樹・茶等の土地利用型農業も盛んであり、農業構造も多岐にわたっている。
平成8年における農業粗生産額は569億9200万円、その内訳けは耕種部門392億0400万円、畜産部門177億1200万円で、畜産は農業粗生産額のおよそ31%を占める地域農業の基幹部門として、酪農、肉用牛、養豚および養鶏がバランスよく発展している。
2.地区の農業概況
地域の農業概要は表1・2のとおりである。|
|
||||||||
|
(単位:戸、頭、千羽)
|
||||||||
| 区分
年度 |
乳 用 牛 | 肉 用 牛 | 豚 | 採 卵 鶏 | ||||
| 戸 数 | 頭 数 | 戸 数 | 頭 数 | 戸 数 | 頭 数 | 戸 数 | 羽 数 | |
| 平成2年 | 164 | 8,360 | 91 | 11,000 | 191 | 124,400 | 120 | 1,647 |
| 最近年 | 134 | 8,490 | 92 | 11,700 | 88 | 83,500 | 64 | 1,640 |
|
|
||||||||
|
(単位:戸、ha)
|
||||||||
| 区分
年度 |
稲 | キャベツ | はくさい | ト マ ト | ||||
| 戸 数 | 面 積 | 戸 数 | 面 積 | 戸 数 | 面 積 | 戸 数 | 面 積 | |
| 平成2年 | 5,126 | 2,148 | 2,862 | 1,235 | 1,694 | 404 | 636 | 23 |
| 最近年 | 4,742 | 2,094 | 2,503 | 1,291 | 1,400 | 348 | 646 | 19 |
3.畜産を核とした地域農業の活性化に関する取組み
- 1) 取組みの背景と動機
- 2) 活動等の状況
豊橋市は、閉鎖性海域の三河湾を控えるとともに、環境対策に対する社会的要望も厳しい地域である。都市化の進展と農業・畜産の発展という両立することが困難な地域のなかで、地域農業を活性化させ、地域とともに発展する農業・畜産を実現することを目標に、畜産を核として地域にある資源を活用した効率の高い農業生産を展開するシステムの構築をはかるため、農家と農協、行政が一体となって取組んできた。
混住化が進む豊橋市で畜産を振興していくためには、都市住民の畜産に対する理解を得ることが必要条件であり、農家個々の取組みだけでなく、地域全体による環境対策を推進することが不可欠であった。一方、地域の耕種部門は多岐にわたり、堆肥に対するニーズも多様化していた。このような状況のなかで、豊橋市酪農業協同組合では、組合員で2つの農事組合法人を組織し、共同処理施設を多数分散設置することで環境対策のシステムを構築し、地域住民の理解を確保するとともに、多様な耕種農家ニーズに機敏に対応できるシステムの形成に努力した。

最優秀賞代表受賞の河合組合長
また、青年部による「豊橋市豊年農業まつり」での乳牛のPR等、各種イベントを通じた消費者との交流活動、婦人部による環境美化運動・料理講習会を通じた消費者との交流活動等、組合あげて地域に向けた積極的な活動により、酪農家の意識高揚と相まって、地域農業の活性化に大きく貢献している。
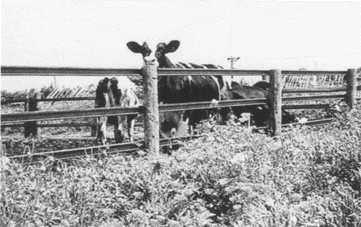
畜産農家の環境美化運動も広がりをみせている
4.家畜ふん尿の処理および利用状況
組合構想の第1陣が豊橋酪農リサイクル組合の設立であり、平成2年度に国の広域畜産環境対策事業を利用して施設群が整備された。当時、全国各地で実施されていた畜産環境対策事業の多くが、拠点となる大規模基幹施設を整備する集中センター方式であったのに比較して、当組合では、地域の特性を活かした堆肥生産の安定と流通を促進するため、各参加農家を地区ごとにブロック分けし、少数グループ単位による中小規模施設を分散設置する方式を採り、それを地域一円に広げていく、いわゆる「豊酪方式」として事業を展開した。この方式を組合あげて強力に推進するとともに、先行して設置した施設で着実に成果をあげることに成功したため、当初は事業構想に懐疑的であった農家らも平成6年に豊橋バイオ堆肥組合を設立し、組合構想に追加参入しており、豊酪方式による事業展開も市内全域に及んだ。現在は、豊橋酪農リサイクル組合および豊橋バイオ堆肥組合の2つの農事組合法人を中心に、組織的な家畜ふん尿の処理が実施されている。2つの農事組合法人によるふん尿の処理過程は、製品の堆肥利用ニーズに合わせて、18ヵ所の処理施設ごとに特徴ある方法を採用している。基本的な処理方法は、各畜産農家から搬出されたふん尿を、処理施設にて副資材(水分調整材:おもにオガコ、モミガラ)と混合して水分60%程度に調整してエア槽でブロアーをかけ、1ヵ月程度堆積して強制発酵させるもので、各施設で平準化した技術となっている。その後、堆積槽で2〜3週間ごとに堆肥の切返しを行いつつ、耕種農家のニーズに合わせて3〜6ヵ月間堆積・発酵している。また、より良質な堆肥利用ニーズに対しては、グループ間で移送・搬入しながら高度に発酵処理し、製品堆肥を仕上げている。これらの堆肥は、市内の耕種農家、総合農協、特殊肥料業者等に流通し、その大部分が市内で利用され、地域内で堆肥利用農家が増加する傾向にある。これは耕種農家のニーズにきめ細かく対応しながら育んだ耕種農家の信頼の事実が反映した結果であり、少数グループ単位に基づく「豊酪方式」の構想がもたらした成果でもある。また、良質堆肥の利用促進のため、豊橋市堆肥マップの作成や堆肥生産情報を耕種農家向けに隔月で提供するなど、ソフト的な面からも弛まぬ努力を続けている。
また、地域内流通の努力に止まらず、袋詰めなどにより付加価値をつけて広域流通をはかる努力も積極的に行っている(図1)。
さらに、酪農家においては、副資材の水分調整材や敷料として経営内でリサイクル利用するケースも増えている。

組合員の牛舎の内部

耕種農家の信頼を得た牛ふん堆肥
5.環境美化運動の特徴
都市近郊型畜産経営においては、畜舎を地域から隔離(樹木の植栽による目隠し)していく方向にあるなかで、当地域では、開かれた牧場で地域住民との調和の持てる酪農経営をめざしている。このため、環境に配慮した畜舎周辺での草花の栽培、樹木の植栽はもとより、「家畜とのふれあい」の持てる憩いの場所として、地域に開かれた牧場作りに積極的に取組んでいる。
18ヵ所の処理施設では平準化した技術で発酵処理される
豊橋市酪農農業協同組合では、畜舎以外の環境美化推進のため、婦人部活動の一環として全酪農家を対象に、環境巡回指導会を関係機関とともに毎年開催し、環境美化意識の高揚がはかられている。また、婦人部活動の特色として、バラ栽培農家(ロックウール栽培)から、改植株を毎年譲り受け(9年、4500株)、牧場周辺への植付けによる環境美化活動を行っている。この活動が肉牛婦人部にも波及し、地域畜産農家の環境美化運動へと広がりをみせてきた。
6.取組みの成果
近隣住民の理解を得るなかで、地域全体においてスムーズに環境整備が遂行でき、さらに、各処理施設の運営管理についても酪農家個々の創意工夫が反映されたため、耕種農家の多様なニーズにきめ細かく対応でき、その結果として、堆肥品質に対する耕種農家の高い信頼を得ることとなった。さらに、豊橋市酪農農業協同組合による包括的な管理のもと、一定水準以上の品質を確保した製品を大量に生産できるようになったため、耕種農家だけでなく流通業者に対する堆肥販売力もつけることができた。毎月開催される2組合の定例会において、各グループごとのふん尿処理状況・流通状況等について情報交換を行い、年間を通じて耕種農家のニーズをいち早く把握し対応している。これにより耕種農家との連携が高まり、また、堆肥を地域の農地に還元する体制ができ、堆肥を通じた酪農家が地域農業システムの一翼を担う位置づけが確立された。
7.その他の特記事項
乳製品の輸入自由化・産地間競争が表面化するほかにおいて、地域酪農の競争力は地の利を活かした「鮮度と良質乳生産」を合言葉に毎日の集乳はもちろん、良質乳生産では、県下23生乳出荷組合のうち7年間にわたって、上位5組合に位置付けられ、他生乳出荷組合(酪農組合等)の範となっている。〈補助事業の実施状況〉
平成2・3年度広域畜産環境対策事業=農事組合法人豊橋酪農リサイクル組合:事業費5億4188万3000円
平成6年度環境保全型畜産確立対策事業=農事組合法人豊橋バイオ堆肥組合:事業費2億0579万4000円
8.今後の推進目標と課題
都市化が今後とも進展することが必須の当地域において、酪農経営を持続的に発展させていくために、酪農家の意識向上と合わせて、当面の取組みとして次の3点に努力を傾注していく。| (1) | 自己還元農地に直接還元できる農家といえども、処理施設の整備を進める。 | ||
| (2) | 地域内の耕種農家との連携体制をさらにはかるため、組織的にも強力に進める。 | ||
| (3) | 堆肥の広域流通体制の確立をいっそう進める。 |
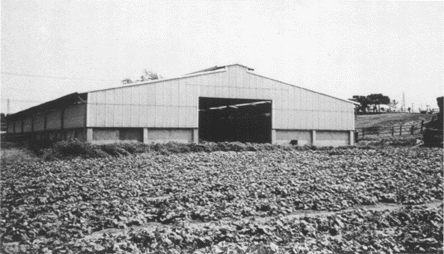
分散設置される堆肥施設
9.愛知県における環境保全への対応状況と今後の対策
本県は名古屋市を中心とする大消費地を背景に抱えていること、食品産業が盛んで豊富な副産物(粕類等)の活用をはじめ、港に近く安価な飼料が入手できることなどから、知多半島や渥美半島を中心に古くからこの有利な立地条件を生かし畜産が盛んに行われてきた。しかし、近年はこれらの地域にも都市化、混住化の波が押し寄せており、近隣住民への配慮が求められていること、購入飼料に依存する経営は堆肥が耕種農家のニーズに合わせた生産を必要とされていること、この両半島に抱かれた三河湾は閉鎮性海域であり、富栄養化対策として条例の上乗せによる厳しい環境規制の適用を受けていることなど、畜産経営の健全な発展のために環境対策は大きな課題となっている。
畜産農家に対しては環境保全に対する個々の努力を促し、責任の所在を明確化するとともに、行政としても畜産経営に起因する環境汚染防止対策指導要領(昭和46年制定)に基づき、環境保全型畜産確立対策推進指導会議を設置し、農家に対する地域指導班による巡回指導や堆肥の需給調整、優良事例の紹介、情報提供などの支援を行い、外部から積極的に支援している。また、一部の苦情発生反復農家に対しては、関係機関が一体となった集中的指導を行い、意識の高揚に努めている。
家畜ふん尿処理の整備に対しても、このような本県の特有の事情から、畜産農家に対しては過大な設備投資が要求されるのが実状であり、行政としても畜産農家をとりまく地域性や土地条件、経営状況、投資意欲等を総合的かつ的確に把握しながら補助事業への誘導をはかっている。
本県では、昭和44年度から県単独補助事業の家畜ふん尿処理対策事業を継続して実施しており、平成9年度までに416ヵ所の整備を行っている。また、畜産環境整備特別対策事業では平成7年度から三河東部地区、平成8年度から豊田加茂地区、平成9年度から三河西部地区、平成10年度から知多地区と県内の各地区のふん尿処理施設を計画的に整備している。また、各地域の状況に応じて環境保全型畜産確立対策事業を実施するとともに、個人施設に対しては各種制度資金や畜産環境整備リース事業の活用の推奨等、今後とも安定的に畜産経営が存続できるよう総合的に環境対策を進めていく計画である。
10.印象コメント
| 1) | 日本一の総合農業地帯のなかでの環境保全型酪農経営
豊橋市の農業は、比較的温暖な気候と名古屋市をはじめとする東西の消費市場に近いという自然的社会的条件に恵まれた立地を背景に、過去20数年来全国1位の農業生産額を誇っている。農業の経営類型についても、施設園芸・畜産を中心とする施設(資本集約型)農業だけでなく、稲作、露地野菜・果樹・茶等の土地利用型農業も盛んである。平成8年の農業粗生産額は569億9200万円で、畜産部門は31.08%を占める。畜産のなかでは、酪農・肉用牛・養豚・養鶏・鶉とバランスよく発展している。当市は、都市化の進展と農業・畜産の展開という相反するテーマが調和している全国でも比類のない地域といえよう。豊橋市酪農農業協同組合は、「鮮度と良質乳生産」を合言葉に、県下23生乳出荷組合中上位を占め、他の組合の範となっているとともに、大農業地帯の土作りに貢献している。 |
||
| 2) | 「豊酪方式」分散型畜産環境整備の成功
処理施設の分散型整備により、地域住民の譲歩と理解をとりつけ、地域全体として円滑に環境整備が遂行された。また、分散する個別の処理施設が酪農家の創意工夫により運営管理され、耕種農家のニーズにキメ細かく対応でき信頼を勝ち得ている。現在、耕種農家の76%が家畜堆肥を利用しており、とくにキャベツ生産への貢献が著しい。 |
||
| 3) | 地域住民と「家畜とのふれあい」型の畜舎周辺環境美化
畜産周辺での草花の栽培、樹木の植栽、日陰樹やベンチの設置を行い、住民との交流がはかられるようにしている。酪農農業共同組合婦人部では、全酪農家を対象に、毎年環境巡回指導会を関係機関とともに開催し、環境美化意識の高揚をはかっている。また、バラ栽培農家と連携し、3年ごとに改植するときに廃棄される改植株(本年4500株)を毎年入手し、牧場周辺に植え付けている。この活動は、一昨年から肉牛婦人部にも取込まれている。 |
||
| 4) | 地域の家畜ふん尿由来の窒素バランス
豊橋市内の家畜ふん尿からの総窒素生産量2684tは、地域内の作目の窒素必要量を超過しているが、そのうち1146.7t(42.73%)が地域内仕向けで、地域内の全作目必要推定量の2121tの54.64%に相当している。地域外持ち出し量は1537.3t(57.27%)であり、地域内の養分バランスに余裕を残している。他の畜種についても、今後、伊勢湾問題を控えて、地域全体の耕地の窒素・リンのバランスには、定量的な留意が必要である。 |