ゆとりある明るく楽しい酪農経営をめざして
新井 肇
◎最優秀賞:経営部門栃木県那須高原今牧場代表 今 耕一 |
1.経営の推移と現況
東京から北に向かう東北新幹線が関東平野の終わりにさしかかると、左前方に那須連山がみえてくる。その中心の那須岳火口から扇状に広がる高原地帯に開拓地が点在するが、その1つが大同開拓である。
黒磯駅から6〜7km、東北自動車道からはもっと近い。近くに遊園地もあり、夏になると牧場の前は観光道路になる。標高450m、降水量1839mm、避暑地であるだけに作物ににとって気候はやや厳しい。
この地は父光雄氏が昭和22年に入植、昭和25年に乳牛1頭を導入、畑作、酪農の複合経営を確立、以来酪農を伸ばして今日にいたったもので、同氏が生まれた年に初めて乳牛が導入されている。
昭和48年に父は同志5人と補助を受けて170頭収容の共同牛舎を建設し、これを利用して成牛34頭の酪農専業を確立して3年目の昭和51年に、2代目の私に経営が移譲された。
経営主となって15年目の平成3年、フリーストール牛舎、パーラーを建設整備し103頭規模となる。
これを機に共同牛舎から独立、同時に地域酪農家13名と北海道に育成専門の会社を設立して、後継牛の育成を自己経営から分離している。
平成8年には3戸からなる任意組合を事業主体にして堆肥発酵処理施設を建設し、ふん尿の完全処理、完全利用体系を確立している一方、平成6年には自分の牧場を法人化し、平成10年には家族経営協定を締結して、内部体制を固め、後は後継者たる長男の卒業を待つだけとなっている。
現在、家族は6人、労働力は本人、妻の2人で、73歳の母は家事と菜園のみに従事している。3人の子供は大学と高校に在学中であり、ほかに最近雇った雇用者1名(女性)がいる(表1)。
このように、近い将来には若い労働力と知恵に満ちた経営になることが期待されている。
2.乳牛育成部門の分離と和牛子牛生産
今牧場は酪農専業で、もう畑作物や稲作は経営には取入れていない。しかし、厳密にいうと酪農から和牛の子牛生産が派生してきて、乳肉複合経営になっている。
それも肥育ではなく、ETによる和牛子牛の生産という珍しい乳肉複合である。
現在経産牛115頭、未経産牛、育成牛の他にF1子牛がいる。和牛育成牛25頭とあるのは初妊牛に和牛の受精卵を移植して生まれた純粋和牛子牛で、販売するために育成中のものである(表2)。
これを生産するにいたった経緯は次のとおりである。
フリーストールで大規模化した今牧場では、計画的に後継牛を育成することが大きな課題となってきた。
そこでフリーストール牛舎が完成した平成3年、ちょうどこの年に事業を開始した(有)北那須牧場に、めす子牛を全頭、北海道へ送って育成部門を完全に切離してしまった。
しかも、現地では和牛の受精卵を移植し、和牛純粋種の子を身ごもった母牛となって帰ってくるという育成と肥育モト牛生産の一石二鳥の効果を狙ったものである。分娩後それを育成し、県内の矢板家畜市場のセリにかける。
和牛子牛の平成9年の販売単価は45万3000円(去勢270〜280kg)、出荷頭数は年間33頭で、ETモト牛では県内第1位の実績を誇っている。
育成部門を切離し、ET子牛生産を取入れたことで、過重な労働からの解放、育成費の節減、優良モト牛の確保、酪農所得の大幅増加という高い効果をあげている。
3.自給飼料とふん尿処理
1) 自給飼料今牧場の所有農地面積は3.6haで開拓地としては小さいが、借入地が8.3haあって経営面積は11.9haとなっている(表3)。借入地の約半分は牧場から500m以内の兼業農家4戸の転作田で、農地銀行の斡旋によるもので、堆肥との交換または賃貸借で文書契約によっている。
残り半分は6戸の非農家の普通畑で同様の契約を結んでいる。施設用地以外はすべて飼料圃で、作付けはデントコーン6ha、イタリアン5ha、混播牧草4.1ha、計15.1haすべてサイレージ化している。輸入粗飼料(乾牧草)も使っているが、TMRである。
TMRの給与はつなぎ牛舎であった時代の昭和57年からとかなり早く、搾乳牛用2種類と乾乳牛用の3種類を作っている。
注目したいのは、和牛子牛の販売成績で平均出荷体重290kg、同日齢320日、日齢増体量0.906kg(雌雄平均)、平均販売単価45万3000円(去勢)となっている。
事故率が5.0%とやや高いことを除けば立派な成績である(表4)。
自給飼料も本格的だが、ふん尿処理においても最近、画期的な施設化を行い注目されている。
それはサイロクレーンを応用した岡本式省力ふん尿処理施設により、クレーンで移動撹拌しじゅうぶんに発酵完熟したものを畑地に還元する装置である。
また、ハウス乾燥施設でじゅうぶん乾燥させたものをフリーストール牛舎のベットに敷料として利用している(図1)。
(図1) 牛ふん尿処理・利用のフローチャート
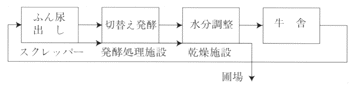
これにより乳房炎の発生が利用前の10分の1以下に激減するという効果があがっている。
4.経営効果
- 1) 技術的効果
- 今牧場の成績は優れているだけでなく、全体にバランスがとれている。これは牛、施設、飼料などの総合的な成果である。
- 経産牛1頭当り乳量は昭和62年7680kg、平成4年8580kg、平成9年8700kg(乳検)と年々向上し、現在平均乳脂率3.98%、無脂固形分率は8.72%と好調である(表4)。
- 2) 収益性
- 3) 財務バランス
- 収益性が高いのは技術的に優れているだけでなく、財務の健全なこととも関係がある。

主催者と歓談する今夫妻
とくに乳質が優れており、平均細菌数は3万以下、体細胞数12万6000個、生菌数5500個となっている。
分娩間隔は394日(13.1ヵ月)、平均乾乳日数は58日で申し分ない。これは全頭を北海道で育成している成果の現われといえる。
所得率は26.4%、経産牛1頭当り所得は24万3000円となり、家族労働力2人で100頭以上の経産牛をこなし、これほどの収益をあげてるというのは見事というほかない。
高収益の要因は何といっても飼料作を共同化で合理化し、育成を分離し、パーラーシステムとフリーストール、TMRで労働過程を省力化して115頭という大規模牛群管理を実現したことと、ETによって初産の借り腹で子牛の高値販売に成功したことである。
搾乳だけでは1万kg以上を搾っても、これだけの所得を実現することはできない。

15.1haの自給飼料基盤をもつ今牧場
〈収益性バランス〉
法人化しているため、貸借対照表が作成されている。
これを、そのまま分析すると自己資本比率21.2%、流動比率107%でそれぞれの基準値30%以上、200%以上を下回ってしまう。
ところが短期借入金は個人から法人への貸付金で実質的には自己資本であるから、これを資本とみなすと、自己資本比率は62.3%、流動比率は824%に跳ねあがる。これは健全中の健全な数値である。
この経営には農協などからの借入金残高があるが、年間償還額の負担は収益性からみても、財務構成からみても問題がない。
飼料作労働は共同作業である。これは平成5年に機械の共同利用のため設立した3戸からなる「上ノ原畜産組合」(任意組合)のグループによるもので、バンカーサイロ(デントコーン)とロールベール(イタリアン)等庭先に運び込むところまで共同化されている。
イタリアンは5月、デントコーンは9〜10月収穫と分散しているが、共同でも適期作業が難しく、将来はコントラクターを使いたいとしている。
5.営農と生活のバランス
収益性もさることながら、今さん夫婦が本当にねらっているのは生活の向上であり、開かれた酪農経営を築くことにある。高原の春は遅いが、私たちが訪れた4月1日の今牧場は入口から牛舎まで花に埋もれていた。
奥さんによると、自分の楽しみだけでなく、観光地でもあるので人にみてもらいたいという気持ちもあってフラワーガーデンをつくり、明るく楽しい雰囲気になるようにしている。
うれしかったのは、通りがかりの観光客が花屋さんと間違えて入ってきたことだという。
ふと入ったのが縁で、この牧場でいま働いている若い女性がいる。月給制、住宅手当あり、週1日、月6日の休暇、働きに応じて能力給、責任手当もある。哺育育成部門を担当、各種研修活動にも積極的に参加を促している。宇都宮市の非農家出身のこの女性は、牛が好きで好きでたまらない、仕事と遊びの区別がないくらいと地元紙に紹介されていた。
こういうよい人を得たのも、今牧場が明るく楽しい酪農をモットーにしてきたからである。
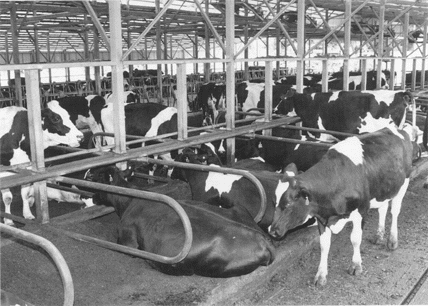
108頭収容のフリーストール牛舎
今牧場の正式名称は「(有)那須高原今牧場ケーアイレディファーム」KIは2人の頭文字「レディ」とした理由は「経営者の今耕一以外は牛も人もすべて女性だから」にある。雇用者を含め全員がイラスト入りの名刺を持っているのには驚いた。
法人化したことで、事務所を設け仕事と生活を分離し、けじめをつけるようにしている。
ヘルパー組合があり、月2回の定期利用をしているが、ヘルパーの人員が整えばもっと休日を増やしたいという。
役員報酬のかたちで本人の720万円をはじめ、妻、母も応分の報酬を受けている。
奥さんは農作業のほかにパソコンによる複式簿記の記帳を担当し、普及センターの記帳グループにも参加している。
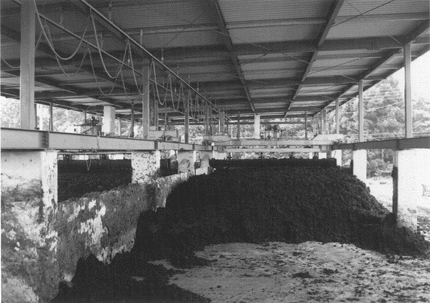
堆肥処理施設
奥さんの役割分担は「経理事務一般、搾乳、哺育育成牛の管理牛舎および周囲の作業環境の整備、労働日誌の記帳」であるが、実はこれは「わが家の生活と農業経営の協定書」に明記されている。
つまりこの経営では法人化しただけでなく、最近、家族経営協定も結んで労働時間や役割分担など法人の規定にないことを取決めている。
このような話を聞いて、今牧場の高い生産性と収益性を支えるものが、何よりも家族関係をだいじにするところからきていることがよくわかった。
6.これからの計画と抱負
今牧場は夢のある牧場である。奥さんも加わりこれからの抱負を語ってもらった。
| (1) | 牛舎も完成したので、乳牛頭数は現状を維持し、今後は北海道の育成牧場で優良乳牛の受精卵移植を行い、質の向上に努める。また、今は子牛で販売しているが、和牛の一貫肥育をめざしたい。 | |
| (2) | 管理の省力化をはかるため、今年(平成10年)中に乾乳牛舎と肥育牛舎を建設する。 | |
| (3) | 牛ふんのリサイクルに力を入れ、周辺農家にも供給したい。また、安全な自給野菜を作り、地域の有機野菜栽培の手本になりたい。 | |
| (4) | 自給飼料は持続するが、共同作業を充実し、将来はコントラクター利用も考えたい。 | |
| (5) | 環境美化、経営環境の改善に力を入れ、酪農の良さをPRしたい。 | |
| (6) | 酪農・農業を体験できる宿泊施設として「ファームイン」の経営、体験牧場をやってみたい。 | |
| (7) | 積極的なヘルパー利用、雇用の導入によって労働時間の短縮、休日の確保に努力したい。 |
要するに今牧場がめざすものは、(1)育成、自給飼料、搾乳とますます複雑化、多忙化する酪農をもう少し整理し、分業化すること。(2)その一方で酪農だけに頼らず、乳肉複合によって経営を多角化すること。(3)環境負荷の少ない、リサイクルできる農業を実践すること。(4)外とのつながりを求めること。(5)営農と生活を調和させ楽しい家庭を築くこと。
長男をはじめ子供たちが次々と卒業してくるこれから、今牧場がどんなに発展するか実に楽しみである。